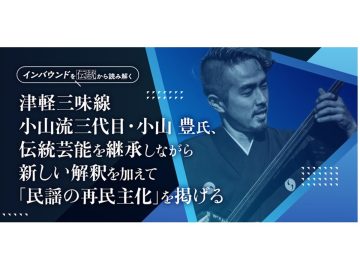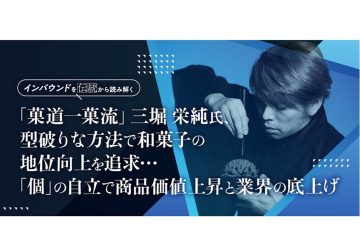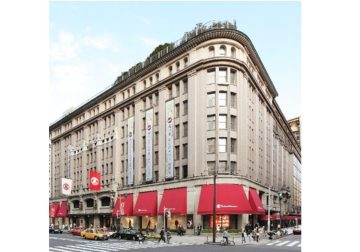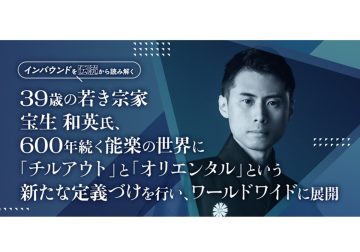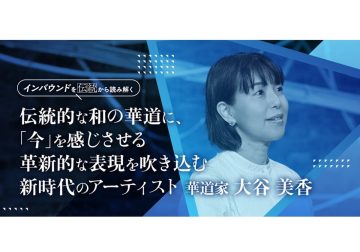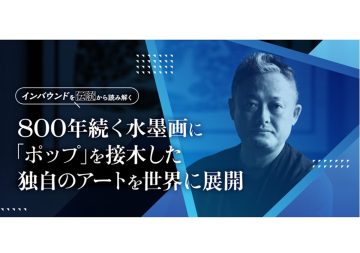●この記事のポイント
・円安を背景に訪日外国人が急増する一方、外資系の便乗や「使わない観光客」の増加など、日本経済への波及効果に課題が浮上している。
・ツアー費用の事前支払い化や「安易な日本食体験」などにより、旅行中の消費や満足度が低下。おもてなしの質の劣化も懸念される。
・地方格差や観光資源の埋没が進む中、行政と旅行業界が連携し、文化体験を軸にした持続可能な観光の仕組みづくりが求められている。
歴史的な円安の後押しもあり、日本は空前のインバンドブームを迎えている。2025年9月までの訪日外客数累計は約3165万人と、史上最速で3000万人を突破。国内経済への好影響が期待される一方、オーバーツーリズムの問題も懸念されている。
円安の恩恵に沸く裏側で、現場は何を懸念しているのか――フランス人観光客を5000人以上アテンドしてきた椎津ニコラ盛光氏に聞いた。
●目次
- 外資系の便乗、“お金を使わない観光客”…インバウンドの光と影
- フランス人がもっとも驚く日本の魅力とは?
- 目先の利益追求による満足度の低下が起きている
- 「京都」対「地方」というインバウンド格差
- 日本人が見せたい「日本」と外国人が見たい「日本」は違う
外資系の便乗、“お金を使わない観光客”…インバウンドの光と影

日本人の父とフランス人の母を持つニコラ氏は、2008年より日本で通訳案内士としての仕事を開始。2013年に旅行会社を立ち上げ、現在フランス語圏の訪日観光客を対象に、少人数限定の団体ツアーの現地手配を手がけている。
フランスの旅行会社から依頼を受け、電車やバスといった移動手段、宿はもちろん、飲食店の予約や訪問先のアポイントなど、来日する観光客の日本国内での手配を丸ごと行い、全日程をアテンドするのがその仕事だ。
コロナ禍を経て旅行業界の浮き沈みを直に見てきたニコラ氏の目に、現在の状況はどう映るのか。
「日本円が安くなったことで、昔から憧れていた日本にやっと来られたという人が増えました。純粋に日本が好きで来る人の割合が増えたのはいいことです。一方でブームに目を付けて、便乗する外資系の業者もかなり増えた。例えばアジア系の旅行会社が、日本で所有している自分たちの宿やバス会社、親戚がやっている飲食店でツアーを組んでしまう。そうするとお客さんは日本の宿に泊まった、日本の物を食べたと思っているけれど、実際は全て外国の企業。それで日本の経済にどれだけ効果があるのかという問題も生まれています」
訪日観光客が増える一方、かつてのような「爆買い」は鳴りを潜め、日本での消費金額は減っているといわれている。それについてはどうだろうか。
「旅行の目的が、物から体験へとシフトしているから当然です。私の扱うフランスのお客さんは、マスアッパー層から準富裕層に入る資産額5000万〜2億円程度の50〜80代がメイン。元々そういう人たちは、文化的な体験を求めて旅行に来ています。買い物は若い頃に十分してきたのであまり興味がない。おそらく訪日観光客の4分の3を占めるアジアの人たちも、こうした旅行スタイルに変化してきている。その過程の中で支出額が減っているのだと思います」
では現在の訪日外国人が実際に日本で旅行中に使う金額は、どの程度なのだろうか。
「私のお客さんだと、大体10万円程度。なかにはほとんどお金を落とさない参加者もいます。なぜかというと今のツアー旅行は、事前に支払う費用に宿代も食事代も交通費も全て含まれているのがトレンド。金額としては航空代を含めて7000〜1万1000ユーロ。今の日本円にすると120〜190万円くらい。旅先に着いた時には、すでに全部込みの高額なツアー費用を払っているので、現地で使うお金としては食事の際にドリンクを追加注文するか、お土産を買うかぐらいで済んでしまうんです」
とはいえ2024年の訪日フランス人客数は年間38万人ほど。全体で見れば1%程度であるため、必ずしもインバウンドの全体像とリンクするとは限らないとニコラ氏は続ける。
「そのなかでも私がなりわいにするフランス人対象の団体旅行はニッチなビジネスです。ただし、観光先進国でもあるフランスの旅行市場は成熟しているので、他国から旅行のトレンドを模倣されることがよくあります。分かりやすい例がミシュランガイド。フランス人が認めることで、世界的な価値に影響が出る。現在、日本ブームは世界中で巻き起こっていますが、ある部分、特に文化的なコンテンツに関してはフランス人が先導してきたと思います」
フランス人がもっとも驚く日本の魅力とは?

ではフランス人から見て、観光地としての日本の魅力はどこにあるのだろうか。
「一つには単純に観光名所の素晴らしさ。中でも神社仏閣、特に神社は日本特有の文化として人気があります。それとアート関連。美術館自体の良さもありますが、日本美術や茶道のように簡素だけど洗練された表現や空間など、侘び寂びを感じられるものは皆さんすごく興味ありますね。しかしもっと根源的な部分で驚かれるのは、日本人の規律(Discipline)と礼節(Civility)です。例えば電車を待つ間もピシッと一列に並んでいるとか、お店のスタッフもお客さんも礼儀正しいとか、そういう国民性の部分。『噂では聞いてたけど本当なんだ!』というのが一つの感動ポイントになっています」
そして大きな魅力の一つが「食」である。しかし今だからこそ、そのあり方を見直す必要があるそうだ。
「居酒屋など大衆的な店に連れて行き、外国人は日本食の良し悪しを判別できないだろう』という前提で、安易に利益を優先する海外の旅行会社も多いのです。だから本格的で伝統的な日本食を実際に体験できる観光客は意外と少ない。日本で実際に手配を担当する、私たちのような会社は、正当な予算を付けてくれと元請けの旅行会社に言いますが聞いてもらえない。そのため朝は宿の食事、昼は手頃に済ませて夜だけ本格的なレストランにするとか、少しでも本物を体験できるように工夫するのですが、日本食の魅力は十分に伝わっていない気がします」
目先の利益追求による満足度の低下が起きている
一方で外国人を受け入れる日本側の「おもてなし」の質にも変化があると指摘する。
「一部ですが、飲食店の対応が悪くなったのを感じています。外国人と聞いた途端に断られることもあれば、料金を釣り上げられることも。なかには飲み放題でしか予約を受け付けず、いざお店に行ったら杯数に制限を付けてきたり、意図的にドリンクの提供を遅くしたり……それくらい露骨なお店もあります」
ニコラ氏は日本の観光業界全体が目先の利益に走り、旅の満足度が下がることを危惧している。
「ホテルの値上げもそう。出張で日本各地に行く国内の営業マンも困っていると思いますが、宿泊費を裏で一斉に釣り上げる談合疑惑がニュースにもなった。コロナ禍で売り上げが急激に落ちたように、観光業はどうしても波のあるビジネス。稼げる時に稼げるだけ稼ごうという心理も分からなくもないですが、それだと確実に先細っていきます。『食事も宿も高い割に大したことない、もういいや』と思われれば、日本の観光地としての価値そのものを毀損する可能性が大いにあるわけですから。
日本本来の魅力を存分に味わってもらって満足度を上げたほうが、長期的には経済的にも大きな効果があるはずです。そうでないとリピーターとしてまた来てくれたり、本国に帰ったあと日本から輸入した商品を買ってくれたり、そういう2次的な経済効果が発生しなくなってしまう。そこが一番の懸念点ですね」
「京都」対「地方」というインバウンド格差
もう一つニコラ氏が危惧するのが、国内における地域ごとの格差だ。
「ありがちなのが歴史ある古都だからと、とにかく京都だけに連泊したがるお客さん。そんなに何が見たいんですか? と聞いても、具体的なアイデアは特にないんです。町が持つブランドイメージによる人気の差が大きい。実際には京都だけだと神社仏閣や庭園ばかりになってしまうので、奈良や彦根、神戸や姫路、広島や岡山などを織り交ぜてツアーを組みますが、それでも東北や北陸にまで行くような旅行にはなかなかなりません」
観光資源としての地方の魅力は、まだまだ埋もれている状態だ。
「大きな課題です。実際に東北地方が外国人に訪問されている割合は、下手したら5%未満です。素晴らしい名所があってもアクセスが悪い。受け入れたいけど道路や法律の制約があって、高額な専用車を手配しないと訪問できない。となると、なかなか足を運んでもらえないんです。地方は国や自治体が柔軟に規制緩和しないと、インバウンドのメリットを公平に享受することができないと思います」
日本人が見せたい「日本」と外国人が見たい「日本」は違う
しかし逆に言えば、埋もれた観光資源を豊富に持つ日本は可能性の宝庫とも言える。
「地方だけでなく季節もそう。私のお客さんで言うと7〜8割が春秋で、特に冬はほとんど来ない。桜と紅葉の印象ばかりで、日本ならではの雪の美しさが伝えられていないんです。以前、伊勢志摩サミットにパネラーとして呼ばれたイギリスの専門家も挙げていたのが、日本人が見せたい日本と外国人が見たい日本には乖離があるという指摘。本当は海外の人たちって、日本人が思う以上に意外なものに興味があるんです。例えば日本の小中学校だってフランス人からすると多種多様な部活動があったり、給食や掃除を生徒自身が当番していたりと全くの異文化。普段の生活や仕事の様子、その地域ならではの工場や社会的な取り組みだって観光資源になり得る可能性を秘めています」
課題は今はまだ埋もれている観光資源を、どうやってお金に落とし込むかだ。
「行政や司法の話になってしまいますが、例えば観光税のようなものをしっかり取ってもいいんじゃないでしょうか。実際にブータンでは1泊1〜3万円の観光税を徴収しています。もちろんオーバーツーリズムの抑制という面もありますが、私としては観光資源を有効活用するための費用として地方に再分配するべきだと思います。
政府や各市区町村がお金をかけて、埋もれた魅力を掘り起こしていく。我々のような旅行業者や専門家とも協力して、それぞれの町が持っている特色を活かすためのシナリオや演出をしっかり立てていく。そういう仕組み作りができれば、インバウンドビジネスはもっと良い形で地域の人々に貢献できるはず。そこが今後の課題であり、可能性なのではないかと思います」
観光業は一過性のブームで終わらせるのではなく、文化の理解と地域の成長を両立させる“産業”へと成熟させる時期に来ているのかもしれません。
(文=米津香保里/経営者の担当編集者)
椎津ニコラ盛光(しいず にこら もりみつ)
日本人の父とフランス人の母を持つツアーオペレーター。2013年に観光旅行の地上手配を行う会社・株式会社イメルションジャポンを創業し[F6] 、これまでに5,000人以上の訪日フランス人をアテンドしてきた。文化体験を重視したツアーづくりで、旅行者の満足と日本のブランド価値向上の両立を目指している。