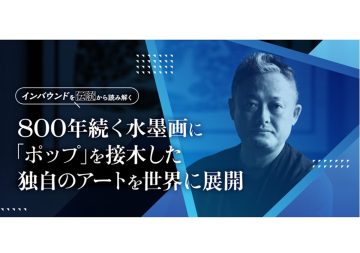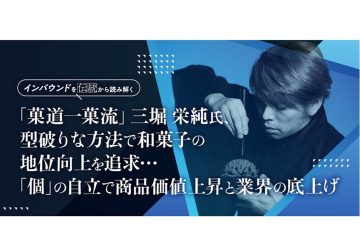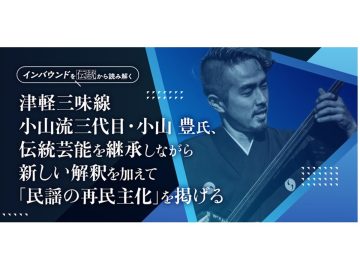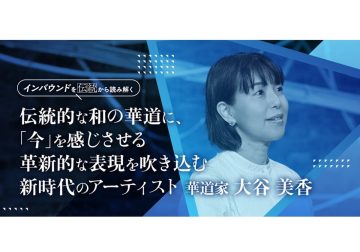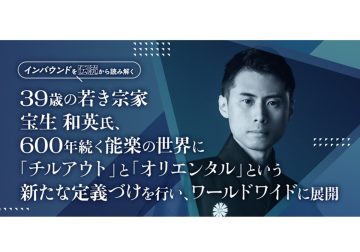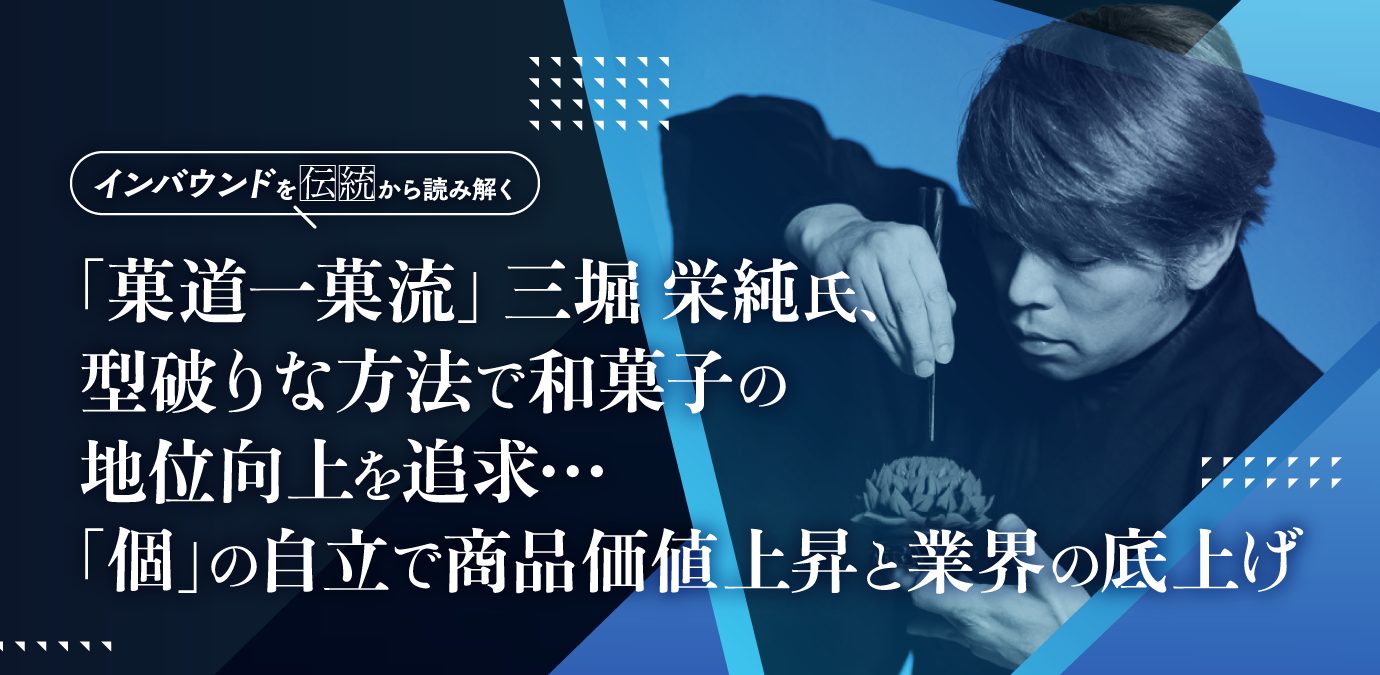
創業70年を超える、神奈川は横須賀の老舗和菓子店の三代目を務める傍ら、繊細かつビビッドな色合いと、凝りに凝った意匠が美しい煉切菓子の製作から提供までの所作を、パフォーマンスとして「道」に高めた「菓道一菓流」を提唱する三堀栄純氏。その活動は日本国内にとどまらず、洋菓子の本場パリで圧倒的な賞賛を浴びるに至っている。和菓子の枠を破り、アウトサイダー的な立ち位置でその地位を高めるべく奮闘する三堀氏に、「菓道一菓流」の形成と活動の真意について語ってもらった。
●目次
「菓道一菓流」のあらまし
――三堀さんが提唱されている「菓道一菓流」のあらましと、始めるに至った経緯をお聞かせください。

和菓子店「和菓子司 いづみや三代目」の経営者として、和菓子が西洋のスイーツに押され、支持を失いつつあることを肌で実感してきました。その状況に対して自分に何ができるかと考える日々の中、33歳の時にテレビ東京の人気番組『TVチャンピオン』に出場することになりました。テレビというエンターテインメントの世界にふれたことで、若いころにミュージシャンを志して活動していた時の感覚がよみがえり、その時に他の和菓子職人との温度差を感じたんです。
菓子作りをエンターテインメント性のあるパフォーマンスとして演出したいテレビ制作の方々に、和菓子職人はうまく対応できていなかった。自分の製作にこだわりを注ぎ入れるのは素晴らしいことですが、テレビ制作の方々も仕事として面白い番組を作るための演出で、作っているときの表情や手元を接写したいと言う。私はその時、テレビ制作の方に「こういう絵が欲しいですよね?」と逆プレゼンしたりしていました。自分なりに、テレビを通して和菓子の世界に注目してもらいたい、盛り上げたいという意図があってのことです。
30代後半を迎え、いづみやが「かりんとうまんじゅう」というヒット作に恵まれたのと時期を同じくして、『TVチャンピオンR』の和洋菓子職人選手権で優勝します。テレビのちやほやなんて持って1年だ、売って売って売り尽くしてやろうと勢い込んで、全国の百貨店を回ってかりんとうまんじゅうを売りまくったんです。そうしたら、家業が危うくなりました。
――何があったのですか?
それまでのいづみやは「三堀商店」のようなもので、50個100個のまんじゅうを作って売っていたのが、あっという間に1万個作るようになっていったんです。すると、その急速な成長に耐えられず、結局は拡大した会社を縮小せざるを得なくなりました。その原因は、和菓子を作る職人不足です。私が製菓学校に通っていた三十数年前ですら、すでに洋菓子クラスが3クラスあったのに対して、和菓子は1クラスしかありませんでした。和菓子は本当に人気がなくて、職人不足になるのは当たり前なんですよね。こうして家業を何とかソフトランディングに導こうと苦労する中で、それとは別に、昔から心の中にあった、洋菓子への嫉妬心が大きくなっていることに気がついたんです。
――洋菓子の「人気」に嫉妬されていたのでしょうか。
人気というより、菓子職人の価値を上げたことに対してですね。三十数年前くらいからパティシエという言葉が出てきて、町のケーキ屋さんがペイストリーになり、シュークリームがシュー・ア・ラ・クレームになり、価格も一挙に上がりました。名前が変われば価格も上がる、これは素晴らしいことだし、業界内の適切なすみわけになると思いました。
スイーツはスーパーでもコンビニでも安く買えますし、ケーキ屋でもチェーン店ならそこそこの価格で買えます。そういうところで買うお客さんと、ペイストリーに買いに行くお客さんは、購買の背景やニーズが違うんですよね。パティシエが作ったケーキが1個800円でも1000円でも、それは価値を認めた方が買いに行くものになっています。つまり、パティシエという言葉1つで、卓越した技術を持つ洋菓子職人の価値が認められる構図ができ上がったわけです。一方、和菓子はいまだにそれができていない。町の老舗の和菓子屋であっても、コンビニで売っているどら焼きより安く売っていることが珍しくありません。ご進物や冠婚葬祭のニーズも減っており、和菓子業界はこの状況に対する明確な答えを出せていません。
そこで気づいたのは、和菓子にも「逆輸入」が必要だということです。洋菓子店の格上げは、パリでの修行経験や受賞歴など、海外で評価されたことが強い後押しになっていました。視野を広くしてみれば、葛飾北斎や伊藤若冲の再評価だってパリのアート界隈が起点になったし、日本刀が注目されたのもハリウッドから。盆栽も抹茶も全部、アウトバウンドで海外での評価を得た逆輸入で、変な話、クールジャパンになったから、逆に日本で受けたんです。これを和菓子でもやろうと思って始めたのが、「菓道一菓流」なんです。
和菓子の世界も個の世界ブランドを確立すべき

――「菓道一菓流」の海外志向は、どのような部分に込められているのでしょうか。
まず、広く販売する商品ではなく、デモンストレーションとしての菓子製作に特化しているところです。たとえばパリの高級ショコラティエは、ピエスモンテというチョコレート製の彫刻を作ります。美術品のようなものを作って、コンクールで優勝すると非常に箔がつく。ロールケーキが1本2000円なら安いねとなるわけで、となればこの構図と同じように、和菓子でも非現実的で非日常的な、ぶっ飛んだ夢の象徴のような作品を作って、ステータスを感じてもらう必要がある。それを「菓道一菓流」の所作であったり、和菓子らしくない、何なら食べ物にすら見えないような、繊細かつビビッドな色合いの煉切菓子であったりが、演出しているんです。
もう1つが、職人の名前を押し出すことです。元々和菓子の世界は「のれん文化」で、たとえば羊羹の「とらや」は有名だけれども、そこで伝統を守りながら工場長を務めている職人の名前や顔は、誰も知りません。一方で、洋菓子はマカロンだったら「ピエール・エルメ」と、職人の名前でブランディングをするわけです。スタープレイヤー同士の競争になると、お客様がそれぞれの価値を高く見るようになるので、価格は上がります。ムーブメントを作るためには「個の世界」にして、「個の競争」をわかりやすく見せないと、あとに続く人に憧れが生まれません。だから私は、いづみやという屋号とは別に、「菓道一菓流」という個人のブランドを作ったんです。この世界観を広めた先に、いづみやの「かりんとうまんじゅう」がメジャーになる未来があるんじゃないかと思っています。
私は、お客様の前で煉切菓子を製作して振る舞うまでの一連の流れを、丁寧にお茶を淹れてお出しする茶道の流れに見立てて、「お点前」と言っています。お点前の時に着る凝った衣装があるのですが、これはハイブランドが出展するパリコレクションからヒントを得たものです。その日常的でない美や価値観を、一菓流に取り込んだのです。
日常的でない日本文化という点では、それこそ茶道という伝統文化の、茶室という空間こそが非日常的なものです。喉が渇いてお茶を飲みたい時に、わざわざ緊張した空間と時間を作り出す、あのお点前に日本ならではの非日常的な美がある。研ぎ澄まされたものが密集している密閉空間で、緊張感も一緒に楽しんでいるんですよね。
茶道のお点前の中でふと気になったのが、ここにもやはり「個の世界」があること。お茶を入れてくださる先生は茶道家で、お茶碗を作ったのは陶芸家、床の間の掛け軸を書いたのは書道家、飾られている生け花の先生は華道家ですね。そして、お点前を始める前に茶道家の先生が書やお花の解説をしていくのですが、そこで出てくる和菓子の説明は、「○○家」ではなく店の屋号なんですね。要は茶室の中で、和菓子だけ一段下なんですよ。だから、他と同じように和菓子も個の世界をブランドにしないといけない、「菓道家」にならなきゃいけないと、強く思いました。
日本文化に伝わる「美しい所作」の集合体

――「菓道家になる」とは具体的に、どういうことなのでしょうか。
まずはお点前の所作を作り込むことから始めました。一番勉強になったのは、大阪の梅田阪急本店に店舗を出して、実演を披露していた時のことです。売り物ではなくディスプレイとして、凝りに凝った意匠の煉切菓子を作っていたのですが、ご覧になるお客様は阪神間の、芦屋や宝塚といった高級住宅地からおいでになった方が多かったんです。和菓子の実演ですから、興味を持って足を止める方の中には、お茶とか着物といった和の文化がお好きな方が多くいました。その中にいたお茶の先生から、ちょくちょくアドバイスをいただくようになったんです。
たとえば「三堀さんの所作は今でも素敵だけど、もっときれいに見えるようにするためには、タオルは常に畳んで置く場所を固定したほうがいいわよ」というような感じで。あとは「前に置いてある道具を取る時には、背中を丸めないで腕を伸ばして取りなさい」とか、道具をまたがないように取ったほうが所作が美しく見えるだとか、細かくいろいろ教えてくれました。その中で、自分の職人仕事を見せるという自覚が生まれたんです。茶道家のお点前も、緊張感を持って所作を見せることがおもてなしでもあるわけで、たとえばお茶を点てる時に、背中を丸めず肩がピッと張った姿勢で行うだけで、凛とした空気が生まれます。美しく見える所作を自分の煉切菓子作りに取り入れたい一心で、バレリーナからも学びました。作ったお菓子をお客様の前に提示する所作を見て、腕の出し方が汚いと言われたんです。バレエでは肩を美しく上げる時には、肩の骨を上げずに腕だけを上げるんだと。だから肩を止めなさいと言われまして、もうすべてが学びでしたね。それらを全部自分の中に取り込みながら、今でも一菓流は形成中なんです。

――三堀さんが心血を注いで形成してきた「菓道一菓流」は、お点前を振る舞われる側に何を伝えているのでしょうか。その魅力についてお聞かせください。
既製品や工場で作られたものには出し得ない、夢のような美しさをたたえた煉切菓子の製作からご提供に至るまで、美しい所作で貫かれている。そのお点前の緊張感と、パフォーマンスとしての完成度を楽しんでいただけると思います。特に評判がいいのは、音楽に合わせて10分で「紅乱菊」を切るパフォーマンスで、またさらに、この極彩色の彫刻のような乱菊を、食べてしまうことが良いんです。どうせ食べてなくなってしまうものを丁寧に盛り付けて、お客様はそのお皿の上を壊したくないように思うけれども、でも壊してしまう。そこに切なさがあり、興があり、楽しみがあるんです。出来上がったばかりの紅の乱菊を、観覧者のひとりに前に出てきてもらって、スプーンをお渡しして、ザクっと入れてもらう瞬間こそ、ご覧になっている皆さんの気持ちが一番高揚するんですよね。言ってしまえば、しょせんはただの餡子なんです。でもそこで皆さんの気持ちが高揚しているから、こんなお菓子はめったに食べられるものではない、こんなに美味しい餡子を食べたことがないと言ってくださるんです。
こんなふうに、お客様の内側でおのずと高い価値を感じてくださるような、そんな見せ方を大衆化していった先に、和菓子店で買ういちご大福はスーパーの出来合いのものとは全然違うと思っていただける未来が来るかもしれない。そう思いながら、私は一菓流の表現を研ぎ澄ましています。なので、私は流派という風に言っていますが、腕のある和菓子職人がそれぞれに、顔と名前が認知されるような見せ方ができればいいと思います。
こんなことを正直に言って、海外でもどんどんパフォーマンスをやったりしているから、業界の中でも非常に叩かれました。私のことを、おもしろくないと思う人もいますが、それはすごくいいことだと思っていて。私をやっつけたい人が出てくれば、そこに切磋琢磨が生まれ、スポーツのライバル関係のようなストーリーが生まれて、往時のパティシエのようなブームができてくるはずなんです。そんな日々の中で、若い和菓子職人の勉強会から講師依頼が来て、100名近くが私の話を聞きたいと集まってくれたのは、すごく嬉しかったですね。これまでに蒔いてきた種が芽吹き出したと、最近は肌で感じています。
オタク的な感性の重要性

――一菓流としての活動は海外でやる機会が多くなったとうかがいました。その中で印象に残ったエピソードをお聞かせください。
海外進出を本格的に考え出した時に、最初に洋菓子の本場であるパリでやりたいと思いました。パリにコネクションがある方に相談したら、その方が「パリには呼ばれるまで行っちゃダメだ」と言うんです。見せてくださいと言ってくるまで、アジアで実績を作れと言われました。
そこでまず上海に拠点を置いて、香港とか台湾を含めて活動しているうちに、ベトナムやタイに呼ばれるようになりました。そこでようやく欧州の視野に入りまして、フランス外務省の後援で開催されるチョコレートの見本市である『サロン・デュ・ショコラ』からお声がかかり、2017年に初めてパリに行くことになりました。すると、ご相談した方から「群れて来るな」と。せっかくパリで和菓子をやるなら、まずはお茶、どうせなら書道、着物と伴って、ジャパニーズカルチャーの総力戦だ……と意気込んでしまうと、先方にはアジアの内輪ノリに見えて冷めるから、絶対にひとりで来いと言われました。
その結果、2017年から19年まで、3年連続で『サロン・デュ・ショコラ』に呼ばれました。2019年は会場のど真ん中にブースを設けてもらいましたね。その3年で欧州に地盤ができたし、やはり欧州で評価されるとその影響が非常に大きいことを実感したので、パリではまたやりたいと思っています。
――最後に、読者に向けてメッセージをお願いします。
和菓子に限らず、日本文化に関心を持って日本に来てくださる方々には、存分に日本を楽しんでいただきたいですね。その時、できればパッケージされていない日本にふれていただけるといいと思います。表面的でない、ちょっとオタク的な楽しみ方と言いますか。和菓子のムーブメントを作るにしても、オタク的な感性は重要だと思います。薄く広く知られたものを、オタク的に深めていく人々が現れることによって、その真価が世界に広まっていく現象があると思うからです。
たとえばお寿司が完全にそうで、まず、今や築地で食べるのと変わらないクオリティの寿司屋が、バンコクにも香港にもあります。そして、寿司がなぜ世界的なカルチャーになったのかと言えば、出発点として大きな役割を果たしたのが「カリフォルニアロール」なんです。カニカマとアボカド、マヨネーズなんかが具材で、海苔を内側にして酢飯で巻いたアメリカ発祥の巻き寿司ですが、出た当時はこんなもの寿司じゃないと言われました。ただ、カリフォルニアロールのおかげで「SUSHI」という言葉が世界中で認知されたのは確かで、そのカウンターとして「本物の寿司を知りたい」というオタクが生まれてきた。そんな彼らが日本の寿司を学びに来て、世界中に本物の寿司を広めていったんです。
これと同じように、私が世界で蒔いている和菓子の種がオタク的な価値観を生み出して、日本の和菓子を見出してほしいですね。そんな逆輸入的なルートも、和菓子の再発見には重要だと思います。
(取材・文=日野秀規/フリーライター)