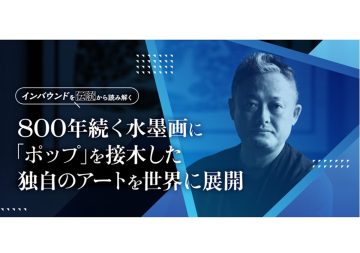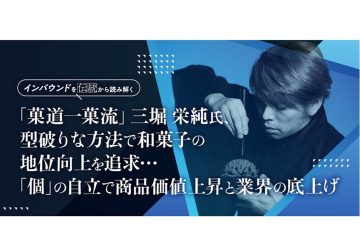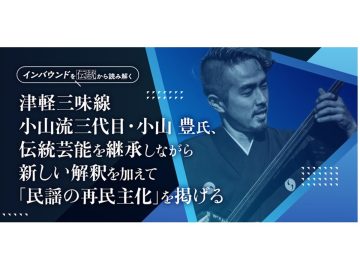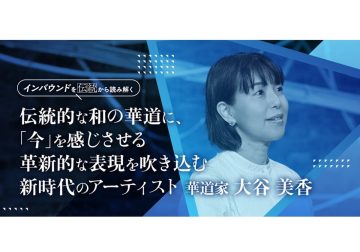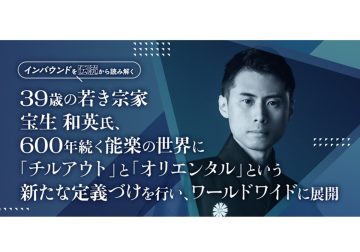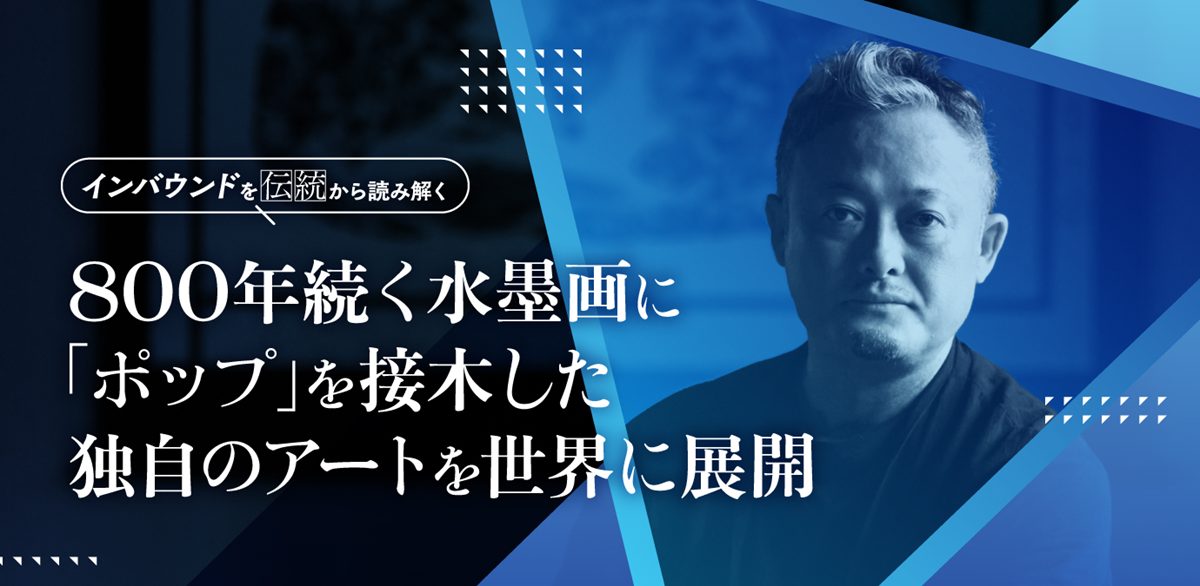
現代水墨画家の土屋秋恆氏は、日本画の「円山派」の祖である円山応挙の流れをくむ古典的な技法を極める一方で、マーカーや蛍光アクリルといった現代の画材を用いた独自のスタイルで知られる。クリスチャン・ディオールやフェンディといったハイブランドとのコラボレーションや、海外著名ブランドのパーティにおけるライブパフォーマンスなどで世界的な評価を受ける土屋氏に、彼の世界の成り立ちから水墨画という日本文化の独自性、インバウンドとの関わりまで、余すところなくうかがった。
●目次
- スタイルの破壊
- 何もない空間に何かがポツンと存在する「侘び寂び」の美と、東京カルチャーとの違和感をあえて演出する
- 「精神と身体の鍛錬」こそが水墨画の本質。インバウンドの爆発的な盛り上がりは、日本文化を海外に伝える好機
スタイルの破壊

――土屋さんが水墨画の世界に入られたきっかけと、積み重ねてきたキャリアについて教えてください。
きっかけは幼少時代に、母方の祖父が岐阜県の下呂温泉で経営していた旅館にさかのぼります。経営の調子がよかった昭和の初期に、祖父が日本画をたくさん買い集めていたんです。それで僕は子どものころ、夏休みになると祖父の旅館に展示されている水墨画をずっと見て回っていました。子ども心に何とも言えない趣を感じて、その時間が僕はとても好きでした。
僕が青春時代を送った1980年代から90年代にかけては、アメカジやバイクといったアメリカ文化が非常に流行していました。僕自身も革ジャンを着てアメリカ製のバイクに乗っていたような育ちでして、仲間内では水墨画に興味があるなんて大っぴらに言えるような時代ではなかったんです。そんなある日、ふとした時に家で、祖父の旅館に飾ってあるような水墨画に興味があることをポロッと漏らしたところ、母が近所に有名な先生がいるようだから遊びに行ってみたらと言うんです。それで高校2年生の時に、それこそバイクをブンブンいわせながら習いに通い出したら、それがめちゃくちゃ面白くて。筋がいいから真剣にやったほうがいいよと先生に言っていただいたのですが、実はその時点で、高校卒業後に1年間、オーストラリアに語学留学することが決まっていました。なので1年間だけ真剣に水墨画に取り組み、オーストラリアに渡りました。
オーストラリアに滞在する間、日本文化の良いところや歴史などを聞かれることがたびたびありました。とはいえ水墨画を1年習っていた程度では、正直何も答えられない。これは恥ずかしい、真剣にやらなきゃダメだと心に決めて、帰国後に改めて師匠にお願いしました。すると、よほど向いていたのか、あれよあれよとたった2年で師範にしていただいたんです。作家として水墨画をやっていくのか、師範として人を教えていくのか、どっちにするか決めなさいと師匠に言われたのですが、はたちやそこらで将来を決められるわけがない。とりあえず、教室と作家活動を並行してやり始めました。
その時もまだ、日本では欧米文化へのあこがれが強くて、日本文化に興味を持っている人は少数でした。21歳の若造が描いた水墨画なんて誰も買ってくれないし、教室の生徒も全員おばあちゃんです。これは参ったな……と思いながら、留学の時に悔しかった思い出も鮮明でしたので、やみくもにチラシを配り歩いて、英語版のチラシを外国の方が多い場所に貼り歩いてと、必死にもがいていました。
――軌道に乗ったきっかけは?
その当時、僕はバンドもやっていたんです。それで、自分のバンドと友人のバンドの幕間に、ライブペインティングをやることにしました。水墨画家はもともと、お客様の目の前で描く「揮毫」をやります。なのでお客様の目の前で、ものすごいスピードで描き上げることを、エンタメとしてお見せできるんですね。これが非常に評判が良くて、ライブペインティングなんて世の中ではまだほとんど行われていない時期でもあったので、外国人向けの雑誌で特集されたりしました。それをきっかけに、見に来る客層がそれ以前とはガラッと変わったんです。スタイリストやヘアメイクなど、ファッション系の感度が高い方々が「やばいイベントやってるね」なんて言って、「ファッションの撮影で協力してほしい」とか、「PVの背景を描いてほしい」とか、「ファッションショーの中で使いたい」とか、さまざまなご依頼をいただくようになりました。彼らとアクセスできたことで、一気に僕の世界観が展開し出したんです。
――古来から受け継がれる水墨画とは趣が変わっていったのでしょうか。
古典の水墨画は、師匠から受け継いだ構図やスタイルをそのまま継承して、同じものを書き続けていくものです。それに僕自身が飽きかけてはいたんですが、かといって変更してしまうことがはたしていいのか悪いのか、というジレンマを抱えていたのは確かです。
ファッション業界はデザインやショーの形態などを、シーズンごとにすべて変えていくものなんです。となると当然、僕に対しても、仲が良いスタイリストが「いつまで同じことやってるんだ、何か違うものはないのか」としきりに言ってきます。「もう同じスタイルは飽きた」と言われて正直腹は立ちましたが、とはいえ自分に対して虚心に目を向けたときに、自分自身でも「もう飽きているな」と思いました。そこで、たとえば墨以外に蛍光色を使ってみたり、アルファベットを書いてみたり、新しい構図にチャレンジしてみたりと、ちょうど師範になって10年目に入ったのを機に、スタイルの破壊を始めました。

――そこから一挙に、クリスチャン・ディオールやフェンディといったハイブランドを筆頭に、ラグジュアリーホテルの展示物やフェラーリのアート、ひいてはローリング・ストーンズの公式Tシャツまで、幅広いコラボレーションを手がけられるようになりました。ヨーロッパにも行かれて個展や講演も行われていますね。
どれもオファーをいただいたものですが、僕が留学をしていて、以前から海外のお客様との関わりも多かったので、英語が使えることが大きかったと思います。英語で講演が不自由なくできて、日本文化を説明できることが、海外展開の際に非常に高く評価していただいた。
1980年代から90年代にかけて多感な時期を過ごした我々の世代は、その意識において過渡期にあったと思います。日本文化や日本の教育など、日本人が持っているバックグラウンドはすべて西洋に劣るという、敗戦国ならではの自虐感を含んだ、日本の重いイメージをまだ背負わされていました。それだけに、「何で水墨画なんてやってるの?」と聞かれることが多くて。日本人固有の美意識を日本人自体が自覚していない時代でしたから、まずそのことが大きな壁になっていました。僕が一生懸命、水墨画は、日本文化はかっこいいものなんだ、素敵なんだと言っても、今でこそ当たり前に受け入れてもらえますが、当時はまったくそんな時代ではなくて。まずは日本語で説明して、理解させるのが大変でした。
何もない空間に何かがポツンと存在する「侘び寂び」の美と、東京カルチャーとの違和感をあえて演出する

――ここで改めて、水墨画とはどのようなアートで、どういう魅力があるのかを、お聞かせいただけますでしょうか。
水墨画は日本へは鎌倉時代(13世紀頃)に禅僧によって伝えられました。それが江戸時代に移る間に、徐々に日本人ならではの「侘び寂び」を感じさせる世界になっていきます。質素さ、静けさ、不完全さの中に美を見出す考え方が侘び寂びです。中国から入ってきたものが日本の中で時間が経ち、日本の美意識によって磨かれてきたわけですが、この感覚は茶道や華道などの日本文化にも共通しています。豪華絢爛(けんらん)主義との対比で、何もない空間に何かがポツンと存在することに美を見る。つまりはそぎ落としの美学で、今の言葉で言うならミニマリズムの極地です。
構図で言うと、あえて余白を残す。西洋画の構図なら、背景はもちろん存在するものとしてしっかり描き込んで完成させるのですが、日本の感性では余白をそのまま書かずに残していく考え方を取ります。たとえば竹を描いている場合、竹の背後に広がる余白に、見る人がかつて経験してきた自分の記憶やイメージを投影することで、見る人が絵を完成させるという考え方なんですね。紙にシミや経年変化による模様が浮いていたら、それに竹の向こうにある山脈を見立てる。いわば借景ですよね。このような、何もないところに何かを重ねて想像することが日本人特有の感性だと思いますし、これが水墨画という文化を形成していると思います。

――土屋さんは、800年の歴史と日本人固有の美意識を背負った水墨画の世界を、現代的な画材を駆使して解釈をし直して、グローバルに展開されています。このような活動の中で、土屋さんが大事にしていることや、チャレンジしていることは何でしょうか。
諸外国と比較した時に、今の日本の町並みは良くも悪くも特殊な状況です。たとえば京都などの古い建築が残っている場所に行くと、数百年前に建造された神社仏閣のすぐ脇に、現代技術の粋である新幹線が当たり前に通っていたり、高層ビルが取り囲んでいたりします。日本人にとっては、あーなるほどねという程度には感じるものの、ものすごく特殊、特異な風景でも何でもない。ごく自然に受け入れられるものですが、これって海外から見ると非常に特殊なんです。これを受け入れてしまう日本人の感性、現代の生活や文化の中に、数百年、千年前の建造物が当たり前にあるという環境が、日本の特殊性だと僕は思っています。
東京の風景に目を転じると、築数十年の古い建物の壁に、ストリートの若いアーティストがグラフィティを描いている。ある意味ヴァンダリズムというか、破壊的な行為ではあるけれども、ストリートカルチャーと古い文化が奇妙に共存している姿でもある。このような日本ならではの風景を水墨画という文化にも取り入れて、ストリートカルチャーと水墨画を隣り合わせて違和感を生みながら、それが自然に見られるというのが僕の目指しているアートです。今の東京そのものを描いているイメージです。
「精神と身体の鍛錬」こそが水墨画の本質。インバウンドの爆発的な盛り上がりは、日本文化を海外に伝える好機

――日本に来られているインバウンドのお客様との関わりでは、これまでどのような仕事をされてきたのでしょうか。
以前から水墨画の教室やワークショップに外国人の方が参加されることは珍しくなかったんです。ただ最近は、インバウンドのブームが定着したこともあって、来られる方の目的や意識が変わってきたと感じます。以前はちょっとした体験のつもりで来られる方が多かったのですが、最近はすでに日本文化を勉強されていて、その上でしっかり学びに来る方が増えています。中には非常に本格的に、1週間連日で集中的にプライベートレッスンを受けられる方がいたりします。アメリカン・フットボールのナショナルリーグであるNFLの某球団オーナーや、Googleの幹部の方も受けられました。
それ以来、Googleはチームビルディングで水墨画のレッスンをしばしば利用していますね。水墨画の1つのスタイルに抽象画がありまして、何かの風景を描くものではなく、与えられたテーマに沿って3~5分くらいで1枚の抽象的な水墨画をさらさらっと描く。これをテーマを変えてどんどん描かせていくと、1回の研修の中でものすごい枚数を描くことになります。結果、その中で自分の内面が水墨画に投影されていくのです。それを資料として使い、チームメンバーに対して「なぜ自分はこのテーマでこの絵を描いたか」ということを告白して、次々と内面をさらけ出していきます。これを順繰りにやっていくことで、チームメンバーの人格を皆が把握することができ、チームビルディングに生きてくるんですね。これはGoogleに限らず、いろんな会社で取り入れられています。
――最後に、国内外のインバウンド関係者に対して、メッセージをお願いします。
水墨画は西洋画とは違って、手を少しずつ少しずつ動かして描いていくものではありません。まっすぐな線をすっと引きたいときには、身体を思い通りに動かさないといけないんですね。長い線を少しずつ、ペタペタ塗るようにして書くのではなくて、ガイドなしにすっと線を引く。これを一発できれいに描くためには、精神の鍛錬と、身体的にも体幹を整えないといけないんです。
なので、ある意味で禅のような思想に近いような、無我の境地で身体をイメージ通りに動かす鍛錬が必要な世界です。自分の精神をニュートラルにして、身体の芯がブレないように、前にも後ろにも自由に行ける状態に体幹を整えて、一気にきれいな線を引くことが大事で、これは体験してもらうととても面白いです。心を落ち着けて、ためらわずにすっと線を引くというところから始まる世界があることを、一度身をもって体験していただきたいし、僕は今後もこのような機会を提供していきたいと思っています。
(取材・文=日野秀規/フリーライター)