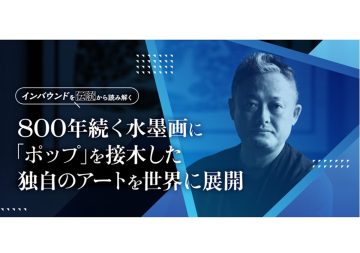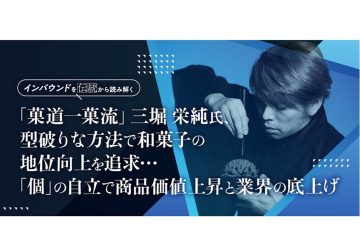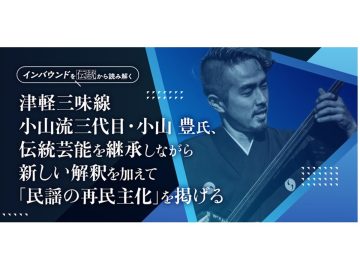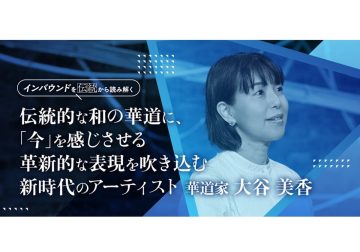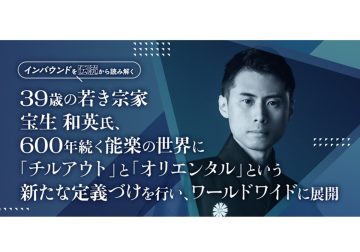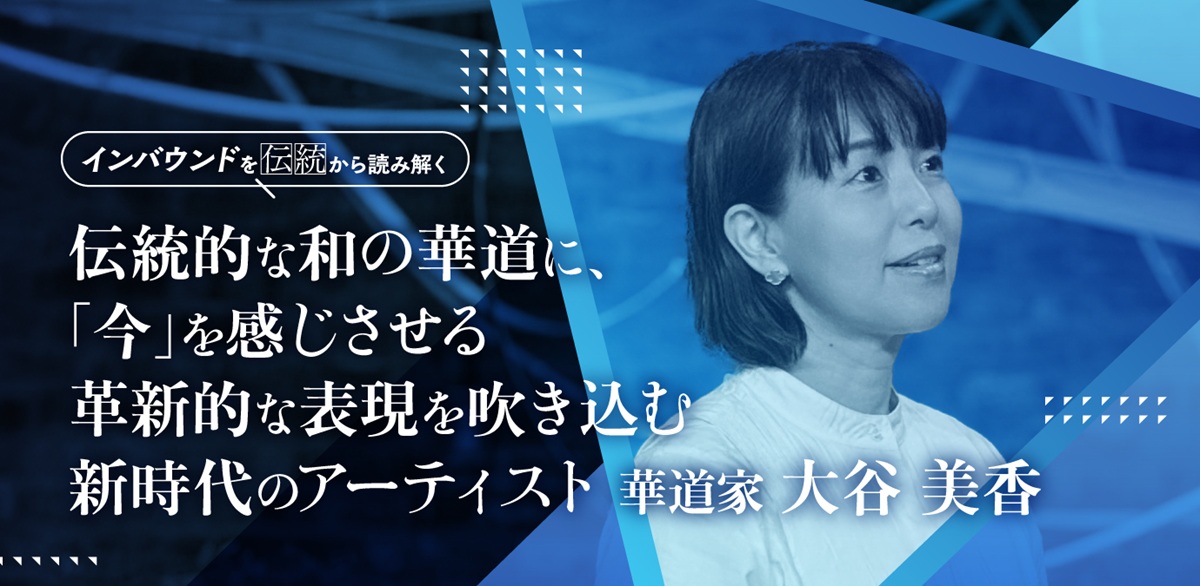
1990年に草月流に入門し、いけばな歴は35年を超える華道家の大谷美香氏。女性誌の編集やスタイリストといった職業を経た後、2011年に華道家として独立して以降、数多くのテレビドラマやNetflixやAmazon Primeなどの配信映画、CMなどでいけばな監修およびいけばな装飾を担当。イベントや広告撮影現場の装飾、いけばなパフォーマンスなども多数手がけている。イノベーティブで芸術的な表現を追求しグローバルに活躍する大谷氏に、自由な草月流のいけばなの世界と、華道家としての活動に込めた志についてうかがった。

――日本文化としてのいけばなと、その中の草月流について、どのような世界なのか教えてください。
いけばなの世界には流派があります。少なくとも200以上の流派があります。いけばなの歴史は、500年以上にも及ぶので、その間にたくさんの流派が誕生しました。草月流は、2027年に100周年を迎えます。創流の理念が、かなり他の流派とは趣が異なると思います。
伝統的なお流派の多くは、古くからその流派に伝わっている花型をすごく大切にして、それを守っていくことに価値を置いています。一方、草月流は初代家元の勅使河原蒼風先生が、いけばなはアートである、という考えで始められました。昔のことを一生懸命守るのはいいけれども、それだけではアートではないという考え方なので、草月流は、花型にしばられません。自由にその時代、世界の空気をとらえて生ける。「だれでも、どこでも、だれにでも」をモットーに、自由な発想でいけばなを楽しめる流派です。生ける人の個性を大切にして、いけばながアートであることを目指すものなんですね。実際に、初代家元はアメリカの「タイム」誌に「花のピカソ」と称されました。そのくらい前衛的かつ自由で、華道界にとっては衝撃的な流派の誕生だったと思います。自由な創作こそが草月流の強さであり、いけばなの世界で支持される理由だと思っています。
たとえばインドに行けば椰子を生けるし、南アフリカに行けばサボテンを生ける。その土地の植物で、いけばなを生けられる。日本で草月流を習った外国の方が母国に帰ったときに、日本の伝統花材を用意しなければいけない、という制約はありません。自由に土地の風土や植生を活かして生けられるのが、草月流の素晴らしさだと思います。今では、世界中に約120の支部があり、世界中で「草月流のいけばな」をたくさんの方が学んでいます。

――大谷さんがいけばなを学ぶことになったきっかけをお聞かせください。
今からほぼ40年ほど前の話になりますが、大学時代にイギリスに留学していた時に、周囲から日本について聞かれる機会が多くて。イギリスの方々にとって、日本は「遠い遠い不思議の国」という感じでした。私にしてみれば、日本は自分が生まれ育った国なので、その文化も当たり前で新鮮味も何もないわけですが、海外の人には非常に不思議なイメージを持たれている。文化も人間も不思議だと思われていて、だからお金を貯めて日本に1度行ってみたいんだと。日本文化にそんなにも海外の方を引きつける魅力があるんだ……と、肌で感じました。自分も日本のことをそんなふうに見直してみようと思った時に、小中学校のクラブ活動で楽しかったいけばなを思い出し、もう一度もっと深くやってみたいと思ったのが学ぶことになったきっかけです。
いけばなを知っていることで、海外の方との交流がより深くなったことが何度もあります。たとえば、オーストラリアのお友だちのお家に行ったときのこと。広いお庭を見ながら、彼女が「うちの庭はあなたに生けてもらえるようなものなんて何にもないのよ」と言うのですが、いざ試しに私がお庭に出てみたら、花こそ咲いていなかったけれど、いろいろな木があり、枝がありました。「全然これでいけばなができるわよ」と言って、私は彼女のお家にあったコップや花瓶を借りて、枝や葉だけを使っていけばなを見せました。そうしたらものすごく驚かれて……こんな文化はオーストラリアにはないと。欧米では、花が必ず主役で、枝や葉は脇役、添え物にすぎず、花がなければ作品はできないと考えられています。
日本のいけばなの考え方は、欧米のフラワーアレンジメントとはまったく違います。そもそも、日本は国土の4分の3が山で、ちょっと郊外に行けば里山が普通にありますよね。ずっと山の中で生きてきた歴史があるからこそ、木や枝を使って美を表現することに長けているのです。なので、花と同じように枝や葉にも美しさを見出すことができて、花がなくてもいけばなはいけられます。ところが、欧米は平原が広がっているところが多く、そこに花を植えて大量に育てることが多く、自然と花に重点を置くようになっています。こんな違いがあるので、欧米で花を使わないいけばな作品を見せるとすごく驚かれて、喜ばれますね。

――日本のいけばなと西洋のフラワーアレンジメントの違いについて、美的な観点、あるいは精神性といった部分でも違いがあったりするのでしょうか。
違いがありますね。たとえば、いけばなの世界では、流木や枯れた花、私たちは「枯れもの」と呼んでいるのですが、そういったものも大切にいけます。木々の根も美しいと感じる。種から始まり、芽が出て、新緑が芽吹き、花が咲き、落葉し、その全ての瞬間瞬間が美しいと感じます。まるで、人間の人生を凝縮しているようだとも、私は感じます。花だけが美しい、と感じるのは、もったいないですよね。まるで、20代だけが人生で美しい、と言っているようなものです。いけばなは、人の人生のすべての時間に美しさがあるということを教えてくれているのではないでしょうか。私は作品に流木をよく使います。流木の形は、人間が作り出したものではなくて、自然が作り出した形です。木が何かのきっかけで倒れ、川に流れて、ゆっくりと海に辿り着く。その長い時間の中であの美しい形が作られます。自然が形作った唯一無二の美しさがとても魅力的です。その木の長い歴史に思いをはせるからでしょうか?
日本画や日本の建築、これは日本の文化全体に言えることですが、空間美、という概念が日本独自の美の概念だと思います。日本語で言うと、「間をとる」という考え方です。海外では空間は何もないもの、という考え方ですが、私たちは、あえて空間を創り出す。海外の花のいけ方は、「とにかく空間を埋める」という考え方がメインですが、いけばなでは、どういった空間を創り出すのが美しいのか、と考える。いけばなで初めに教えられるのが、どういう間の取り方に緊張感があって、美しく感じられるのか、人の心に訴えかけるのかということです。空間美をすごく考える。海外では、空間は「単に何もない」ということになりがちですが、、日本では空間が美になる。もう真逆ですね。
東日本大震災を機に、いけばなに人生をかけて取り組むことを決意
――留学から戻られて、20歳の時にいけばなを始められたんですよね。それから就職をされて、順調にキャリアを積んでいく中で、いけばなを生業にされたのは大きなキャリアチェンジだったと思います。
きっかけは、2011年の東日本大震災でした。私は東京にいたのですが、東北の状況に大変なショックを受けました。当時、一番つらかったのは、非常にたくさんの方が亡くなったこと、それにはたくさんのお子さんも含まれていたことです。自分は東京にいて、生き残ったことが申し訳ない……というような気持ちになりました。たまたま残され、命を与えられた私たちが、これからの毎日をもっと意味があることに使わないと、亡くなった方々に申し訳ない。本当にやりたいことを今やらないと、自分だってこの先はわからない、そういったことが、ぐるぐる頭を駆け巡りました。いけばなについては、ずっと教室を開いて教えたい、とは思っていました。ただそれを本気で仕事として取り組んでいくことは、先延ばしにしていました。当時の仕事もあるし、いけばなが仕事として成立するかも分からないし、やりたい、とは思いながら、多分本気で仕事にする覚悟はなかったと思います。それが、「今やりたいことをとにかくやってみよう」と動き出しました。
今でこそいろいろな仕事を頂けるようになりましたが、東日本大震災の後、最初に教室を開くと生徒さんは5人だけでした。あの時は、それでも来てくれたことがありがたくて! あれから教室は大きくなり、今はたくさんの生徒さんに来てもらっていますが、あの時のあの気持ちは忘れてはいけないと、今でも肝に命じています。「1人でも多くの方にいけばなを伝えたい!」と切望していたので。
現在は、アーティストとしてのお仕事をたくさん頂けるとようになって、スケジュール的に教室をやるのがギリギリではありますが、それでも初心を忘れず、教室は死ぬまで続けていきたいと思います。
――アーティストとしての活動は、具体的にはどのようなものになりますか?
企業からの依頼でいうと、例えば、昨年はペリエ・ジュエというフランスのシャンパン・メゾンのイベントが印象に残っています。ペリエ・ジュエはアート支援に力を入れている会社で、中でもフラワーアートをとても大切にしています。それで毎年のイベントでは必ず、1人のアーティストに作品提供を依頼していて、去年は私にご依頼いただきました。
会場は、1階と2階があり、それぞれにアートを提供する、というコンセプトでした。1階の作品は巨大で、幅5メートル奥行き15メートル、もう会場内がすべて花という状態です。ゲストの方がフラワーアートの中に埋もれるようなイメージです。誰も見たことのない森のようなインスタレーションを制作しました。使用した花は、5000本以上。SDGsの観点から、伐採されて廃棄予定の木を譲り受けました。ペリエ・ジュエのイメージカラーである淡いピンクと白で着色して、会場に設置。会場に入ると、不思議な木がたくさん林立しているようなイメージです。これに5000本の花を合わせて、1階に自然界には存在しない色合いの空間を作り出しました。ゲストの皆さんは、花のアートに埋もれながらシャンパンを味わうことができます。2階にも、また別のフラワーアートを制作したのですが、これにはロスフラワー500本を使用しました。規定より短すぎたり曲がりくねってしまって、市場には出せない花たちです。このロスフラワーをゲストの皆さんに手に取っていただき、1人1本ずついけてもらいました。皆様が花を持って、どこに生けようかと考えながら会場をぐるぐる回っているその姿が美しい。人が花を生ける姿、それこそがアートであるというインタラクティブアートを提供しました。

―― 一般に思われているいけばなの世界を大幅に拡張した、コンセプチュアルな空間アートを手がけられたんですね。
一番最近のものだと、今年の5月に中国の杭州で巨大な作品を作りました。25m×25mのプールに水を10センチくらい張って、その中で踊りながら花をいけました。ダンサーを従えて、エンターテインメントとして群舞のいけばなショーをやりました。これはYouTubeで公開しているので、ぜひご覧いただきたいです。

――中国を含むアジアと欧米、あと日本で、いけばなの受け止められ方に違いはあるでしょうか。
日本では、いけばなは、言葉が先行していて、みなさん知っているようで、でも詳しくは知らないというような、そんな感じだと思います。禅のような静謐(せいひつ)な雰囲気で、床の間に置いてあるものというような、そういったぼんやりとした既成概念がとても強いです。草月流のいけばなは、そういったイメージとは、全く違うので、「今のいけばな」というものを、「もっといけばなは自由であるといこと」を伝えていきたいと、いつも思っています。一方で、海外だとこの既成概念という敵がいないので、のびのびとできるような気がします。私の作品をネットで知ってくださり、アーティストとして認めてくださったら、あとは好きなように表現してください、と自由にやらせてもらえます。
それぞれに異なるやりがいを感じながら、日本でも海外でも、常に挑戦していきたいと思っています。草月流の教科書の最後のテーマが、「いけばなに今できること」です。この言葉がいつも頭に引っかかっているといいますか。今の私にできること、今しかできないこと、私にしかできないこと、それは何なのだろう? と常に考えています。いけばなという伝統を伝統のまま置いておくのではなくて、その伝統を終わらせたないためにも、革新が必要なのではないかと考えています。このAI主流の時代に、伝えられるいけばなの魅力とは、何なのだろうかと。

――海外から観光で日本に来られる方々との関わり合いはあるでしょうか。
観光客の方々がいけばなを体験できるコースを設けて、教室でお弟子さんたちに教えてもらっています。元々は私が英語が得意なので、教室を始めた時から観光客を受け入れていました。民泊のマッチングサービス大手のエアビーアンドビーが手がける「Airbnb Experience」という、体験プログラムの紹介サービスがありまして、私が日本代表としてLAのローンチングパーティーに参加したこともあります。なので、海外の方にいけばなを知っていただく活動には、今でもすごく思い入れがあり、お弟子さんに引き継いてやってもらっています。それとは別に通常の教室には、日本在住の海外の方がたくさん習いに来てくれています。師範の資格を取ると、そのお弟子さんたちが、それぞれの国に帰国し、いけばな教室を立ち上げてくれます。そうすると、またそこでいけばなが広がっていく。お弟子さんの教室の様子をSNSで見ると、とても幸せな気分になります。
――最後に、海外の読者および国内のインバウンド関係者に向けてメッセージをお願いします。
日本の文化を知りたいと思ってくださり、その中でもいけばなに興味を持っていただけるのはとても嬉しいことで、大歓迎です。私どもが提供するいけばな体験コースは、しっかりといけばなの技術をお伝えさせていただくので、体験、というよりも、しっかりお稽古していただく感じになります。
短時間に体験して楽しいというだけなら、いけばなをやっているふりと言いますか……剣山に2本ぐらい花を生けて、これがいけばなですよ、とするのは簡単です。ただ、せっかく来ていただいたのだから、しっかり学んで帰っていただきたい。草月流の教科書は、空間の作り方を学ぶために、まず伝統的な花型から習うように構成されているのですが、その一番大切な花型を、花型図(設計図のようなもの)を見ながらいけていただく、というレッスンをやっています。私の表参道のアトリエで行いますので、アトリエを実際に覗ける、というのも面白いのではないでしょうか?
今まで、300人以上の方にお越しいただいています。国や年齢も本当にバラバラで、お花が大好きな小学生もいるし、ずっといけばなをやるのが夢だったと言ってくださる老夫婦もいらっしゃいます。
かなり前から予約を入れられる海外のフローリストの方や建築家、デザイナー、美術関係の方も多いです。グループレッスンは6人までと少人数なので、その人その人のペースを守りながらできると思います。プライベートレッスンのご希望もあり、それも個別にお受けしています。ぜひ日本に来た時には、いけばなを体験していただきたいですね。
(取材・文=日野秀規/フリーライター)