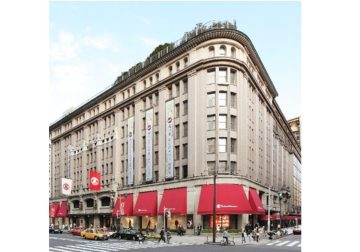●この記事のポイント
・中東・湾岸諸国からの訪日客が急増、昨年(24年)は4万人を突破
・若い世代を中心に先発隊として日本に来る人々が増え始め、SNSでの発信情報を見て「自分も行ってみよう」という人をさらに増やしている
・滞在中の消費額が数千万円に上るケースも珍しくない
1~3月の訪日外国人客が四半期としては初の1000万人超えとなるなど(日本政府観光局<JNTO>の発表による)、相変わらずインバウンド熱が冷めやらぬなか、中東・湾岸諸国からの訪日客が急増している。2016年には年間で2万人に満たなかったが、昨年(24年)は4万人(JNTO推計値)を突破した。1回の滞在でグループで数千万円を消費するケースも珍しくないというが、増加している理由は何なのか。また、日本の事業者側としては今後も増加が見込まれる中東諸国からの訪日客を取り込んでいくためには、どのような施策・対応をすればよいのか。専門家の見解を交えて追ってみたい。
●目次
富裕層旅行者の基準をクリアしている方が多い
インバウンド事業を手掛ける株式会社ジェイ・リンクス代表の金馬あゆみ氏によれば、もともと中東では日本の漫画やアニメに慣れ親しんで日本に親和性を感じている人も少なくなく、日本は「いつかは行ってみたい国」の一つになっていたという。そうしたなかで若い世代を中心に先発隊として日本に来る人々が増え始め、彼らのSNSでの発信情報を見て『自分も行ってみよう』という人をさらに増やしているようだ。また、最近ではインフルエンサーが主催するツアーや、20~30代の若い世代が立ち上げた、従来はなかった新しいかたちの旅行会社が増えてきていることも影響しているという。
「以前から日本に高い関心を持つ方々は存在しましたが、その数は年々増加しており、リピーターも多く見られます。また、日本に関する様々な情報が以前と比べて中東の人々の目に触れやすくなっており、関心を持つ層が広がっています。大阪・関西万博では中東各国がパビリオンを出展しており、パビリオン関係者が「ブレジャー」(ビジネス+レジャー)として親族を伴って日本に滞在するケースもあります。さらに、万博を訪れた旅行者のSNSの投稿を見て、『万博開催中に行こう』という動機で訪日する方々も増えています」(金馬氏)
中東・湾岸諸国からの訪日客の属性や、旅行スタイルにはどのような特徴があるのか。
「一般層であっても年収1,000万円を超えることは珍しくなく、近年では社会進出する女性も増加しています。そのため、航空券代を除いて旅行1回あたりの消費額が100万円以上という、JNTOが定義する富裕層(高付加価値)旅行者に該当する旅行者が多いのが特徴です。他地域と比べて旅行の手配を旅行会社に依頼するケースが強く、また子どもの多い家庭が一般的であるため、家族旅行における1回あたりの総額が大きくなる傾向があります。VIP、VVIPのお客様となると護衛やメイドなど同行者も増えるため、必然的にホテルの部屋数や食事の量も多くなり、1回の旅行で数千万以上の消費となることもあります」
また、最大の楽しみの一つである買い物においては、いわゆる爆買いと呼ばれるような行動もしばしば見られます。ハイブランドに限らず、化粧品や医薬品、食品、漫画・アニメ関連グッズ、そのほか日常使いできる雑貨など、短時間で数十万円から数百万円を購入される例も珍しくありません。食事においても、例として鉄板焼き店では人気の和牛で追加注文が相次ぎ、1グループの会計が100万円を超えるケースも見られます。
日本は商品のバリエーションが非常に豊富で質も高いため、そこに魅力を感じられるお客様も多いです。中には買い物目的で、家族全員で数十個のスーツケースを持参するケースも見られます。また、漫画・アニメ・ゲーム関連のイベントや期間限定ショップを目的に何度も日本を訪れる熱心なリピーターも存在します。」(金馬氏)
スピードと臨機応変な対応が重要
では、日本の事業者側としては、増加が見込まれる中東諸国からの訪日客を取り込んでいくためには、どのような施策・対応をすればよいのか。
「中東・湾岸諸国は、今後の伸びしろと消費額の大きさでは非常に魅力的な市場と言えます。しかしその一方で、日本側で提供される商品・サービスや接遇のあり方が彼らのニーズと合っておらず、誘客に結び付いていないことも少なくありません。特に食事面においては、ハラール対応が実状以上に厳しく困難なものとして捉えられている場合が多く、本来であれば少しの調整で十分満足されるケースであっても、受け入れを過度に難しいと判断され、機会を逃してしまうことがあります。
近年では、初来日でもゴールデンルートに限らず地方への訪問を希望される旅行者も増えてきています。しかし、例えば旅館においては洋朝食のご提供が難しければ滞在が難しく、近隣で他の宿泊施設が見つからない場合は、その地域への訪問自体を諦めるといった、非常に惜しいケースも見受けられます。
また、日本の観光事業者においては『あれも知ってほしい』『これも体験してほしい』と、中東の旅行者にとっては過剰に感じられるほど、多くの要素を説明や観光コンテンツに詰め込みすぎてしまう傾向も見られます。さらに、貸切など特別対応が難しかったり、確認に時間を要して返答が遅れたりすることで失注に至るケースも少なくありません。この市場では、スピードと臨機応変さ非常に重要であるため、それを意識した対応が求められます」
(文=BUSINESS JOURNAL編集部、協力=金馬あゆみ/ジェイ・リンクス代表)