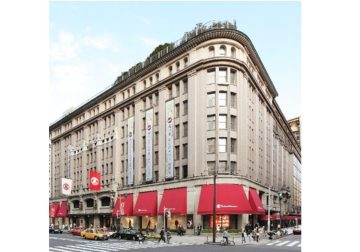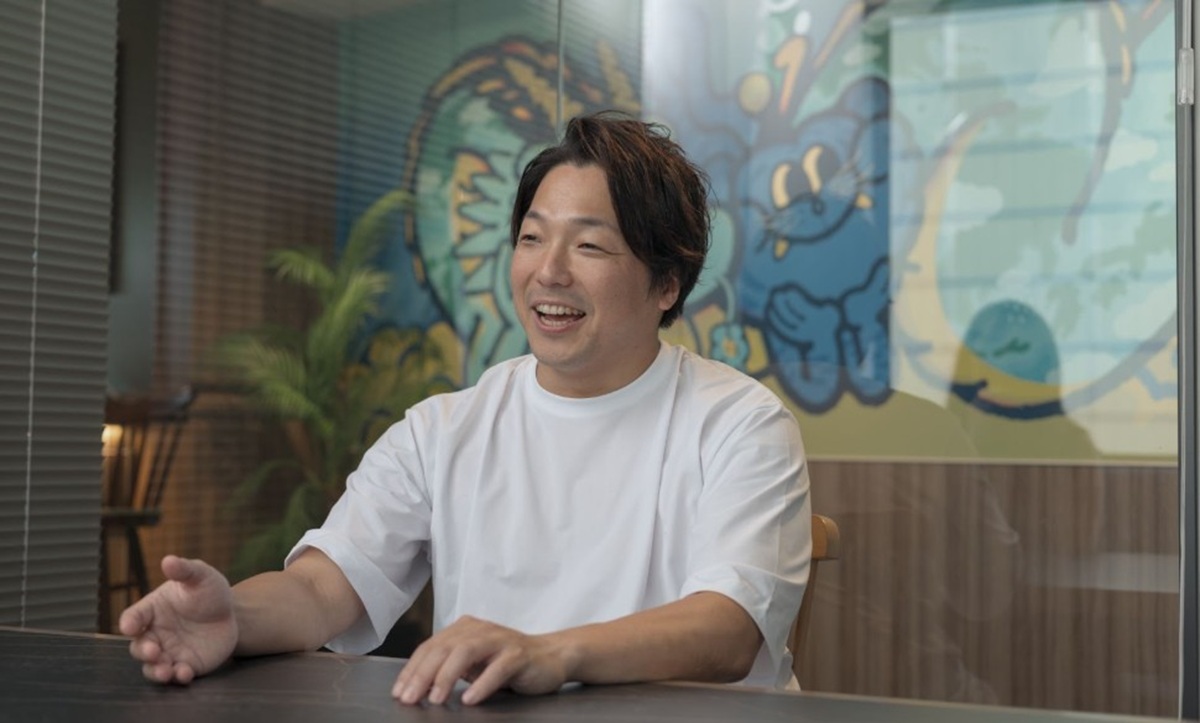
インバウンド需要の高まりにより、日本が盛り上がっている昨今。東京や京都などの有名観光地に外国人観光客があふれる一方、観光資源が豊富ながらも観光客不足や人材不足に悩み、くすぶっている地方都市も多く存在します。
そんな日本国内で起こる格差に課題を感じ、自社の強みで地方を救い、日本を世界一に押し上げようとする企業があります。
今回は、グローバルタレント紹介事業や訪日観光事業などを手がけるインバウンドテクノロジー株式会社 代表取締役、林 秀乃佑氏にインタビュー。
インバウンドテクノロジー社が、なぜインバウンド事業に取り組み、どのような展望を描いているのか、そのビジョンと戦略について、詳しくお話を伺いました。
●目次
日本は世界一の観光大国になれる!その理由とは

——インバウンドテクノロジー社は2023年から訪日観光事業「Trip In」を立ち上げていますよね。グローバルタレント紹介事業からスタートし、訪日観光事業に目を向けた理由を教えてください。
訪日観光事業に対する世界的な盛り上がりがあることに加え、我々のこれまでの事業との親和性が高いことが理由です。
現在、観光業の盛り上がりとともにインバウンド市場に大きな注目が集まっていますが、実はインバウンド事業は、日本人にとってそれなりにハードルが高い事業なのです。
たとえば、ベトナム人向けのインバウンド事業を行おうとしたらベトナム人の雇用を、タイ人向けならばタイ人の雇用を、というように目的に合わせてさまざまな国の人材を雇用する必要があります。しかし、言葉の壁もあり、各国の人材を広く雇用できる企業は多くありません。
インバウンドテクノロジーは、すでにグローバルタレントに特化した人材紹介事業を10年ほど行っています。現在は日本語レベル、技術レベルがともに高いIT人材の紹介を主軸としていますが、自社でも20カ国以上の方々を雇用してきた経験があり、社員皆がグローバルタレントと一緒に働くことに対して違和感を持っていません。
グローバルタレントを自社で雇用して組織化できるという我々の強みを生かせば、全世界に対して日本のよさを届けていけるのではないかと考えています。
——インバウンドテクノロジー社が訪日観光事業をスタートした2023年は、すでに日本でのインバウンド事業はかなり盛り上がっていたようにも見えます。まだまだ、日本のインバウンドには可能性があるのでしょうか?
私は、「日本が世界一の観光大国になる」と考えています。訪日観光市場は、まだまだ伸びしろが大きい領域ですね。
現在、世界一の観光大国はフランスで、年間8000万人以上の外国人観光客が訪れ、オリンピック・パラリンピックが開催された2024年には1億人を突破しています。一方、日本は2024年に外国人観光客数が過去最高を記録しているものの、3600万人にとどまっています。
一見、まだまだフランスに差をつけられているように見えますが、私が「日本がフランスを超えられる」と考える要因には「観光の基礎条件」があります。
これは、「気候」「自然」「文化」「食事」の4つに加え、「安全・安心」「交通・アクセス」「宿泊施設」「観光情報」の合計8つの、観光を成り立たせるために重要な要素のことです。
日本でいえば、観光客の興味を引く四季折々の変化、各地の郷土料理、時間にも正確な充実した交通網などですね。
この8つの要素が、バランスよく高スコアで維持されている国は、日本しかありません。
インバウンド業界が注目する東南アジア

——インバウンドテクノロジー社が、Trip Inでインバウンド需要にどのようにアプローチしているのか教えてください。
団体ツアーのお客様と個人旅行客のお客様の2方向からアプローチしています。団体ツアーのお客様は、タイやベトナムを中心に中国、台湾、インドネシア、オーストラリアなど、世界各国の旅行代理店上位100社ほどと連携して、代理店が販売しているツアーの日本でのオペレーションや手配を行ったり、一緒にツアーをつくったりしています。
個人旅行客のお客様に関しては、陶芸や日本酒、祭りなど、日本独自の文化に触れられる、旅行者のニーズに合わせたコンテンツを用意していますね。こちらは、おもに富裕層がターゲットです。
たとえば、発展途上国では、働きはじめてから年収がやや上がったタイミングで、ツアーを使って日本に旅行しよう、という動きになります。その後に年収が上がった方やそもそも富裕層の場合は、すでに何度か日本に来ていることも多く、ツアーで主要な観光地に行くのではなく、少しニッチな場所に行ったり体験をしたりということを求めるようになります。
2方向でのアプローチを進めている理由は、そういった、国の経済事情やライフステージによって変化する旅行のニーズに対応するためです。
——とくにターゲットにしている国などはあるのでしょうか?
2方向においてターゲットになると考えているのはタイやベトナムです。団体ツアーのお客様も、個人旅行をされる富裕層のお客様も多く、ターゲットとなる方々の母数が多い国です。今後、富裕層になりうる若い方々も多い、非常にパワーがある国という印象があります。
中国や台湾、香港、オーストラリアなどはすでにツアーは使わない方が多いので、富裕層向けの体験型プランのターゲットになります。
インバウンドテクノロジーの全世界対応と送客力が地方を救う
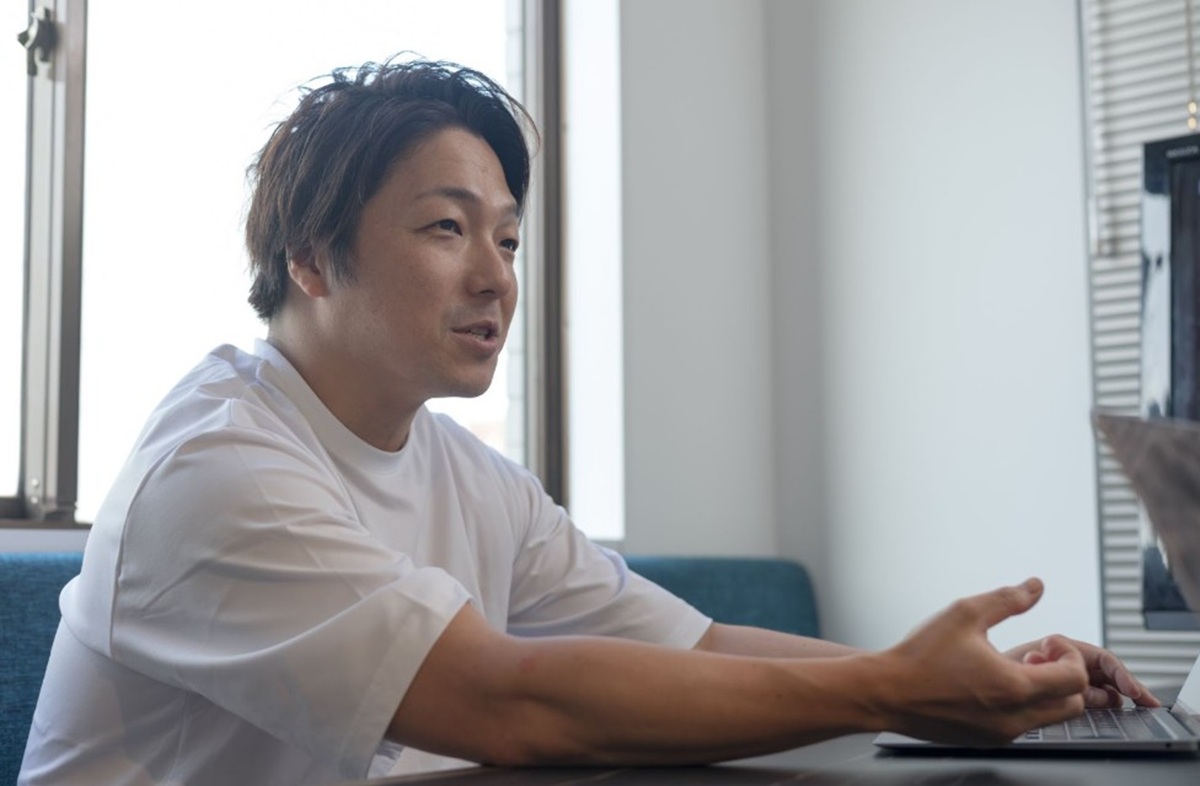
——インバウンドテクノロジー社が持つ、他旅行代理店などとの差別化のポイントはどこにあるのでしょうか?
実は、他国の旅行代理店からの依頼を受けて手配を行うランドオペレーターという事業は、数十年前から存在するビジネスです。しかし、ランドオペレーター企業は中国専門、韓国専門というように、単一の国を対象としていることが多いのです。
インバウンドテクノロジーの場合、国や言語を問わず採用してマネジメントできるため、全世界が対象になります。
とくに、日本と距離が遠かったり、馴染みがなかったりする国のほうがランドオペレーターを使いたがる傾向にありますが、そういった国の場合、対象外になっているランドオペレーター企業が多いのです。
日本全国どこへでも、求められている言語が話せるガイドやオペレーターを配置できるのは、大きな強みだと考えています。
——インバウンドテクノロジー社は、宿泊事業もスタートさせていますね。
そうですね。中伊豆にグランピング施設、伊豆高原に民泊施設を開業しています。実は伊豆は私の出身地でもあるのですが、宿泊事業を自分の出身地でスタートさせたのには、インバウンドテクノロジーが真に目的とする「地方創生」が根底にあります。
そもそも観光客が減少するなか、外国人観光客も訪れずにくすぶる地元の様子を見て、日本の各地にそういった場所がたくさんあるのだと感じました。
オペレーションやプラン作成でしっかりと外国人観光客を誘致し、さらにそこに“過ごす場所”をつくる。そうすると、外国人材対応のための人材も必要になるだけでなく、地域に雇用が生まれます。
我々が持つ強みを生かした事業同士を循環させ、経済性を維持しながら日本が抱えている社会課題を解決していけるような会社になるためのスタートとして、まずは日本各地と同じく課題を抱える自分自身の出身地を盛り上げたいと考え、宿泊事業の最初の地として選びました。
実際、すでに地方自治体と組んで外国人観光客誘致を行うツアーも進められています。
2026年3月にベトナムから福島へ、1000人の観光客をチャーター機で誘致するツアー計画が進行中です。
地方の空港は海外との直行便がないケースも多いので、なかなか外国人観光客が来ないのですよね。そういう場合、チャーター機での誘致は非常に有効です。
インバウンドを一気通貫で抱える未来へ

——最後に、インバウンドテクノロジー社の今後の展望や、事業展開などについて教えてください。
我々が目指す、インバウンドを軸とした地方創生のため、グローバルタレント紹介事業、訪日観光事業などを連携させた垂直統合経営を確立させていきたいですね。
また、事業間の連携だけでなく、外国人観光客誘致の際に必要になるバスやホテル、飲食店事業などを行えるように事業拡大していければと考えています。宿泊事業はこの先駆けですね。そうすることでツアーの際も自社サービスで囲い込むことができるようになります。
また、テクノロジーの力でサポートできるポイントを拡大していくことも考えていますね。具体的には、旅程を組んだり、料金を算出したりなど、AIが対応するシステムなどを構築して、我々だけでなく多くの旅行代理店が使用できるものを提供することで、さらなる販路拡大も行う方針です。
*
外国人材との共生に強みを持ち、インバウンド業界に新たな風を吹き込むインバウンドテクノロジー社。
自社の強みを循環させながら、地方の眠れる魅力を世界に発信し、日本を世界一の観光大国へと押し上げようとするインバウンドテクノロジー社。その挑戦に、今後も注目が集まります。