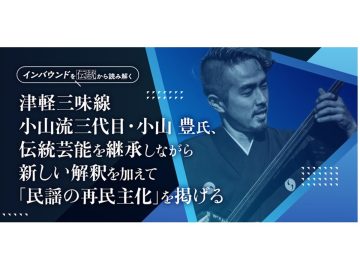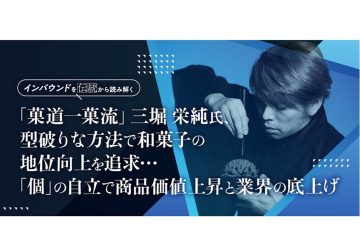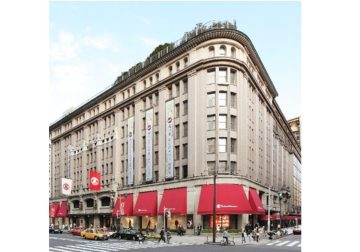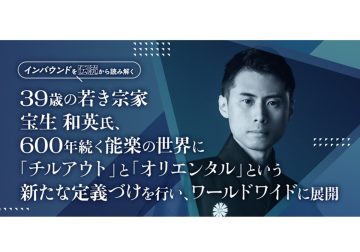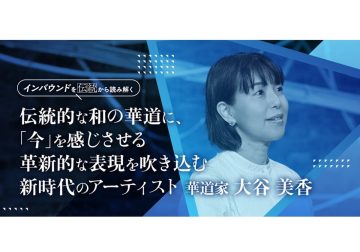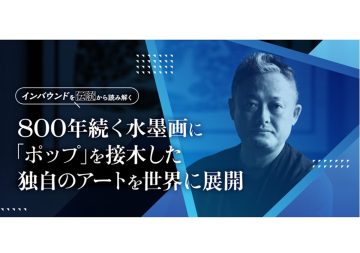●この記事のポイント
・観光業の人手不足・オーバーツーリズム・低生産性という三重課題に対し、現場の構造から解決を図る取り組みが進んでいる。
・季節や地域に応じた人材マッチング、非観光地のグランピング施設開発など、新たな観光需要の創出が動き始めた。
・DX導入による生産性向上や外国人ワーキングホリデー活用を通じ、持続可能な観光産業への転換が進む。
「一生モノの『あの日』を創り出す。」をコーポレート・ミッションに掲げ、国内観光分野に特化した人材サービスと、非観光地における観光施設の開発・運営事業を展開する株式会社ダイブ。2024年に東証グロース市場への上場を果たし、観光業の課題解決のため、さらなる業容拡大を進めている。
同社の創業メンバーであり、代表取締役社長を務める庄子潔氏に、現在の観光・宿泊業が抱える構造的な課題と、その解決に直結した事業ポートフォリオについて詳しく聞いた。
●目次
- 空前のインバウンドブームの陰で静かに進行する危機的状況
- 観光業の抱える課題の解決がビジネスモデルの中核であり、すべてのサービスで「ウィンウイン」を追求する
- ITを活用した自社の「人海戦術からの脱却」という経験を、商材である人材サービスに活かす
空前のインバウンドブームの陰で静かに進行する危機的状況

――2002年に観光施設に特化した人材サービスで創業されてから、現在は地方創生事業にも手を広げていますね。近年はインバウンドのボリュームが拡大して、観光業界も潤っている半面、課題を抱えているとも聞きます。
庄子氏 ご承知の通り、観光業は日本における数少ない成長産業の1つです。コロナ前、2019年の観光業の市場規模は約27兆円でした。このうち約22兆円が日本人の観光消費で、インバウンドは約5兆円。この両方がコロナでいったん消滅してしまったわけですが、現状はコロナ前を超える成長となっています。
政府も観光立国というスローガンを打ち出し、2030年までに市場規模を37兆円まで拡大する目標を立てています。その中身は、日本人の消費は22兆円のままと見込み、インバウンドをコロナ前の約3倍、15兆円まで伸ばすと。昨年ですでに33兆円を超えているので、いたって現実的な目標と言えます。
このような成長の陰で、課題がいろいろと生まれているのは事実です。まず1つ目が、当社の主な事業分野である人材、労働力の不足。次に、観光客が訪れる地域が偏ることで、集中した観光需要が地元の方々の生活を脅かしている「オーバーツーリズム」の問題。最後に、観光業の労働生産性の低さ。この3つが、私たちが認識している観光業の課題です。

――人手不足についてですが、具体的にはどのような形で問題となっているのでしょうか。
庄子氏 ホテルや旅館などの宿泊施設のスタッフが足りていません。というのも、観光需要の高まりを受けて、宿泊施設の建設ラッシュと新規開業が続いているのに、働く人は増えていないから。観光業の従事者は、2019年の時点で約65万人でした。このうち、コロナ禍の間に15万人ほどが離職されて、いまだに戻り切ってはいないんです。
この理由は、まず正直なところ、決して待遇がいい業界ではないこと。加えて、観光地は地方立地であることが多いので、若者は都会に出てしまい、地域の労働人口自体が少なくなっていることもあります。
やはり働く場所としての魅力を高めて、他の業界から宿泊業に転職してくるような活力ある業界にしていくことが必要です。宿泊業はプロフェッショナルとして、お客様の応対をするホスピタリティ業なので、仕事にやりがいを感じている方は少なくありません。そこでやっぱり大事になってくるのが待遇で、実際に待遇改善を続けている施設は増えてきたという印象がありますね。
観光業の抱える課題の解決がビジネスモデルの中核であり、すべてのサービスで「ウィンウイン」を追求する

――観光客の訪問地域が偏ることによるオーバーツーリズムについて、お考えをお聞かせください。
庄子氏 1年中混み合っている京都や、あるいは冬場のニセコなどが代表的なところですが、インバウンドのお客様が集中しています。通年で約3700万人に及ぶ外国人観光客を、意図的に分散させるための施策は、これまでとられてきませんでした。その結果、いわゆる観光公害とも評されるような課題が出てきてしまっています。
考えてみれば当然の話で、初めて行く国ではやっぱり定番のところに行きたいというのは、世界共通の人情ですよね。つまり、リピーター観光客に対して、いかに定番以外の観光地を訴求するかがポイントだと思います。ただ、実はこの数年、日本人でも意外に思うようなところにインバウンドのお客様が来られるようになってきています。たとえば岩手県の盛岡は、米国のニューヨークタイムズに「訪れるべき観光地」として紹介され、インバウンド客が増加しています。このような流れを本格化させる努力が必要です。
――もう1つ課題として挙げられていた宿泊業の労働生産性ですが、なぜ低いのでしょうか。そして、これによってどのような問題が起こっているのでしょうか。
庄子氏 結局のところ、宿泊業は人力で何とかする、労働集約型の業種になっているんです。たとえばフロントの仕事でも、宿泊台帳を紙で管理している施設はいまだに少なくありません。紙ベースだと集計まで人がやらないといけなくなりますが、IT化されていれば台帳の管理はもちろん、データ化から分析まで自動化することが可能。これだけで人1人当たりの生産性が全然違ってくることは明らかなのに、とりあえず人を配置して、お客さんがいっぱい来るからどんどん採用しようみたいな施設が、実は多いんです。この非効率を解消できれば、当然、待遇改善のための原資が捻出できますよね。
ただ、このような現状には理由があります。ホテルや旅館は上り調子の産業ではあるものの、その7割程度が、従業員十数名から100名未満の中小企業。いきおい、一人ひとりが何役も担わないと回らないというふうにならざるを得ません。たとえば旅館の女将は、お客様への直接のおもてなしに加え、従業員の動きにも目を配り、全体に気を配るというのが本来の女将業です。それが家族経営の温泉旅館となると、女将が集客のための観光ポータルサイトとの交渉もやり、当社のような人材会社にも対応してとなったあげく、本来の業務に集中できない。結果として、形式的な対応に終始してしまうことがあり、本来の魅力や価値が十分に発揮されないのは残念に感じます。
――観光・宿泊業が抱える課題について伺いましたが、これらに関連する貴社のサービスについて、ご紹介いただけますでしょうか。
庄子氏 まず人手不足については、弊社の主力事業であるリゾートバイトのサービスがお役に立てていると思っています。これは全国規模で観光・宿泊施設のデータベースと、人材のデータベースの両方を構築し、効率的にマッチングさせるプラットフォームです。地方ではそもそも労働人口が少ないうえに、若者がいないことも多いのですが、弊社はその部分の補完ができることが最大の強みであると認識しています。
あと、宿泊施設にはどうしても季節性がつきものです。山間部の温泉旅館は紅葉の時期が繁忙期で1年のピークになりますが、それ以外の時期は比較的余裕があります。スキー場は12月から3月がピークで、それ以外の時期はスキー場が閉まるので従業員はぐっと少なくていいとか、夏の海も同じことですね。このような季節性があると、1年を通して正社員を雇用し続けるのは、経営的にも厳しい。この点、弊社のリゾートバイトなら季節性に応じて人員配置を実現できます。
リゾートバイトの場合、働き手にもメリットがあります。まずは知らない場所、非日常のリゾート施設で働く物珍しさや楽しさといった魅力が味わえることと、そこでの出会い、ひいては新しい自分の発見まで、さまざまな可能性が広がっているのがリゾートバイトです。そのうえ、金銭的なメリットもあります。リゾートバイトは原則として住み込みになるので、住居は無料で提供されますし、食事もまかないで無料です。つまり、生活費がかからないので効率的に貯金ができるのです。
地方には若い人が少ないと言いましたが、年配の方でリゾートバイトを希望する人も最近は増えていまして、もちろん若者と変わらない働きをされています。弊社では50歳以上の方をシニアと呼んでいますが、たとえば仕事をリタイアされて、自分の趣味や好きなことにつながる働き方をしたいと。バイクが好きなシニアの方でしたら、高原のホテルに住み込みで働き、休みの日にツーリングをしたりとか。ゴルフが好きな方なら、ゴルフ場で仕事をして休日にはゴルフ三昧だとか、スキー場でも同じです。こんなふうに、自分のライフスタイルに合わせてリゾートバイトをする人がすごく増えています。
――宿泊施設と働き手の双方にとって、メリットを見出しやすい働き方ということですね。もう1つ、地方創生事業はどのようなものでしょうか。
庄子氏 これは観光需要の集中を緩和する試みと捉えています。弊社の地方創生事業は、平たく言うと観光地でない場所、非観光地で観光ビジネスを行うものです。この非観光地とは何かというと、箱根や軽井沢のように名の通った観光地ではなく、一般的には観光地と認識されていない地域、場所をいいます。このような場所の自治体とタッグを組み、既存の施設や場所を活用・リメイクして、観光客が集まる施設として訴求するのが、弊社の地方創生事業です。
弊社の取り組みは、地方の自治体の方にもメリットがあります。地域と継続的・多様な関わりを持つ「関係人口」と、観光や出張など一時的に地域を訪問する「交流人口」の両方を増やすことは、高齢化や人口減少に悩む地方の自治体にとって、今や死活問題。
そこで弊社は、自治体が保有している遊休地、たとえば昔使っていたオートキャンプ場みたいな施設や土地とかお借りして、弊社が企画からウェブメディアを活用した集客、施設オペレーションまで一気通貫でグランピング施設を運営します。施設の名前を「ザランタン」といいまして、現状は全国6か所まで拡大。自治体にとっては、遊休地の活用に加え、交流人口・関係人口の増加、地元産品の消費拡大、雇用創出といった効果が期待できます。弊社と自治体がウィンウィンでやっていく形が取れていると、自負しています。
――労働生産性の問題について、リーチするサービスはあるでしょうか。
庄子氏 大手宿泊施設向けに、人材管理システムを展開し始めています。大手の場合、グループで年間に採用するスタッフの数が、アルバイトや弊社のような人材会社を経由した人も含めて、数百名から1000名を超えるような規模になることも。そのため、人事部ではスタッフの管理に非常な労力と時間を割かざるをえない現状があります。
この部分を、弊社の人材管理システム「ハッサク」を導入していただくことで、業務効率化を図ることが可能です。それまで手作業だった人材管理作業に、ITを導入して省力化・時間短縮を可能にするサービスを普及させて、業界の労働生産性向上のお役に立ちたいと考えています。
――現在の観光・宿泊業の成長には、インバウンドの拡大が大きいとお聞きしました。貴社の地方創生事業のポートフォリオには、外国人人材の活用事業もあるということで、その点についてご紹介ください。
庄子氏 弊社では、ワーキング・ホリデー制度を利用して来日される外国人人材の活用に力を入れています。これは簡単に言うと、長期の観光に来ている外国人に、滞在資金を稼ぐことを認める制度です。日本は現在、世界30か国とワーキング・ホリデーの協定を結んでいて、相手国としてはオーストラリアやニュージーランド、カナダ、韓国、台湾、香港など。ヨーロッパや南米の多くの国とも相互協定を結んでいます。
弊社はワーキング・ホリデーを使って来日する方々に、リゾートバイトを紹介しています。彼らは日本での生活や文化を体験しながら働きたいと考える方々で、住まいと仕事の両方を提供できる弊社のサービスは、そのニーズに非常に適しています。半年働いた後に残りの期間を観光に充てるなど、働き方や過ごし方を柔軟に選べる点も魅力です。こうした自由さと利便性が評価され、多くの方にご好評をいただいています。
ITを活用した自社の「人海戦術からの脱却」という経験を、商材である人材サービスに活かす

――お話を伺っていると、貴社の事業において、ITが大きな武器になっていると感じます。
庄子氏 武器にすることができたのには理由がありまして、そもそも弊社はバリバリの労働集約型の会社だったんです。何でも一人ひとりの働きで解決する。困ったことがあれば人を採用して、人海戦術で何とかするという体質の会社でした。ところがコロナで、観光という営みそのものが止まり、弊社も大きな打撃を受けました。人を抱えているがゆえの苦悩も経験しました。
そこで認識した経営課題として、労働集約型であることが問題であると。もちろん、日々のオペレーションの中で、どうしても人が担わなければいけない部分はあります。でもそれ以外はできるだけITの力を使って効率化を図り、知識集約型の会社に生まれ変わることで、収益力を上げる取り組みを続けてきました。それがしくみやノウハウとして社内に蓄積してきたので、お客様にもサービスとして展開しようという形で、進化してきたものです。
――労働集約型の会社でDX(デジタルを活用した事業変革)を行った成果は、業績にはどのように表れているのでしょうか。
庄子氏 2025年6月期の決算では、売上高が約137億円、経常利益が約7.6億円となりました。どちらも過去最高なのですが、コロナ禍の直前は売上高が約76億円で、経常利益が1億円弱だったんです。この間に、売上高は8割増え、経常利益は7.6倍になりました。利益率が大きく向上したわけです。
これには不採算事業の撤退も寄与していますが、やはり一番は、IT化によるオペレーション改善とか効率化をやってきたこと。外からはビジネスモデルが変わっていないように見えても、実際には中身が大きく様変わりしています。
――今後の事業展開についてお聞かせください。
庄子氏 冒頭でお話したように、観光業は日本国内での数少ない成長産業です。なので、今会社の調子がいいからといって、むやみに海外展開などに手を広げるよりは、インバウンド領域も含めて伸びる領域にこだわっていきたいと考えています。その中で、新事業も構築中で具体的な内容はまだ公表できませんが(笑)、人材サービスと地方創生事業とのクロスセルを伸ばしていき、「観光・宿泊業のパートナーといえばダイブ」というブランドを作り上げていきたいと考えています。
(取材・文=日野秀規/フリーライター)
・リゾートバイトダイブサービスサイト:https://resortbaito-dive.com/
※こちら主軸事業のサイトです。
・地方創生事業サイト:https://dive.design/region
※こちらザランタンのサイトです。
・ハッサク:https://lp.ha-saku.com/
※こちらが記事中にもある派遣管理システム「ハッサク」のサイトです。