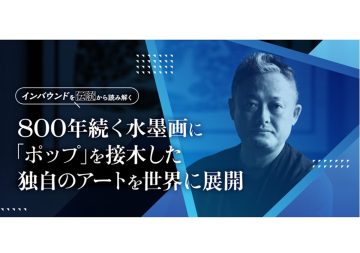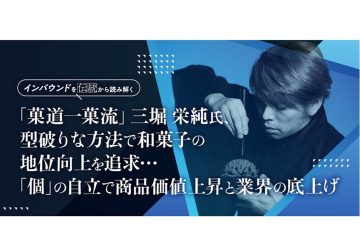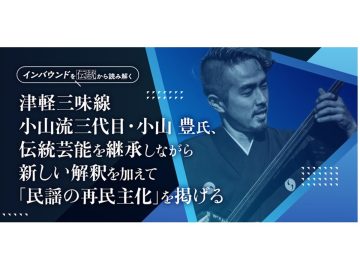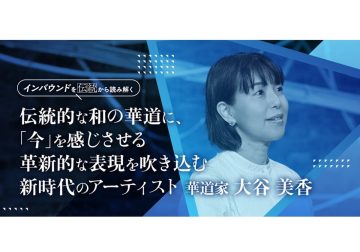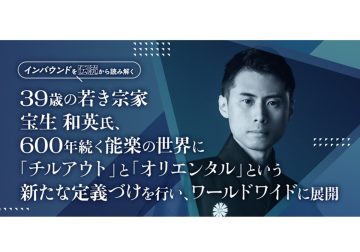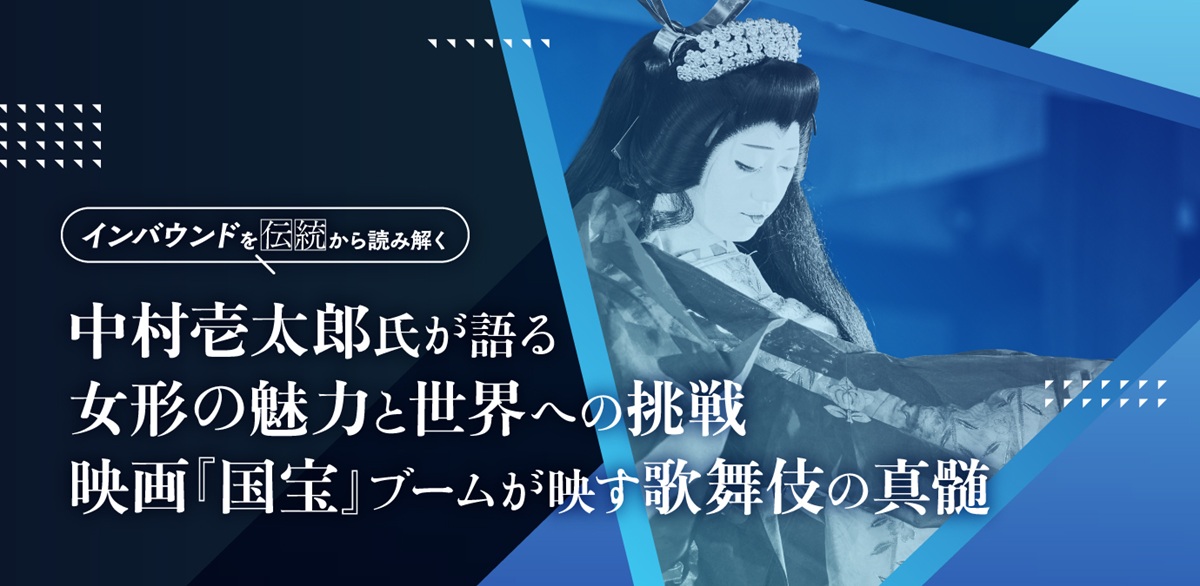
父は歌舞伎俳優の四代目中村鴈治郎、母は日本舞踊吾妻流宗家の吾妻徳穂、父方の祖父は人間国宝の四代目坂田藤十郎、祖母は元宝塚女優の扇千景という、歌舞伎をはじめとする芸能一家に生まれた中村壱太郎氏。日本の伝統芸能の筆頭格である歌舞伎の中でも、特に花形といえる女形で確固たる実力を示し、日本舞踊でも吾妻流七代目家元を務める「歌舞伎界のホープ」に、大ヒット映画『国宝』の裏話から伝統芸能としての本質、氏と海外とのかかわりに至るまで、余すところなくうかがった。

――壱太郎さんは歌舞伎を追求しながら、現代演劇やメディアへの出演、そして海外公演まで積極的に行われています。これまで歌舞伎俳優として積み重ねてきたキャリアについて、改めてお聞かせください。
私は歌舞伎の家系に生まれましたが、私の家は父で4代目と、歌舞伎の中では比較的若い家です。これがたとえば市川團十郎のお兄さんは13代目で、中村勘九郎のお兄さんのお父上の故・中村勘三郎のおじさまになるともう18代目になります。そしてもう1つ、上方歌舞伎の流れを受け継いでいるという点にも特徴があると思います。私は東京生まれですが、父までは京都出身です。そのご縁もあり、関西での公演に積極的に参加させていただき、研鑽を積んできました。
その中で、上方歌舞伎出身の片岡愛之助のお兄さんに可愛がっていただき、愛之助のお兄さんの相手役として、私の女形人生が始まりました。妹の役になったり、恋人の役になったり、妻の役になったり、いろんな役の経験を積ませていただくと同時に、祖父である四代目坂田藤十郎はじめ上方の女方の大先輩方からの指導も得て、女形として鍛えられていったと思います。
私は中村壱太郎という芸名で初めて舞台に立ったのは4歳のときで、およそ30年前になります。大学を卒業した13年前から、本格的に歌舞伎俳優としてやっています。そして、母方が吾妻流という日本舞踊の流派を家系としており、私が吾妻徳陽として、7代目家元をして務めております。習い事としての日本舞踊は、宗家である私の母が主に教えておりまして、私は舞台や映像作品などにおける舞踊の創作や、振り付け、指導などを主に行っています。

――指導といえば、いま話題の映画「国宝」では、お父様の四代目中村鴈治郎さんが歌舞伎指導をされていますね。
父は吉田修一さんが原作を執筆される時から協力していまして、映画でも指導という形で入っています。そして、振り付けとして吾妻徳陽の名で私が参加しているのですが、実際に歌舞伎のシーンを事細かに再現するお手伝いをさせていただきました。
――そうなんですか!
「国宝」で演じられる演目はすべて女形の演目でして、父は立役、つまり男役の役者なものですから、私にお声かけいただいたんです。ただ、あくまでも歌舞伎指導は父で、私は舞踊の指導という立場でさせていただきました。
「国宝」の大ヒットを受け、歌舞伎座が新しいお客様でにぎわうほどの反響をいただいています。ただ、これは歌舞伎を題材にしているから、歌舞伎を高いレベルで再現したからというより、やはり「国宝」というドラマ自体が多くの人に響いて、海外でも注目されていると思うんです。ドラマを表現する1つの媒介、手法として歌舞伎を使い、結果としてそれが非常に良いマッチングになったのだと思います。

――壱太郎さんはご自身のインスタグラムで、試写の感想として「家とは、自分とは、歌舞伎とは、自分がやるべきこと、なすべきこととは……」という内容を記されていました。どんな風にお感じになったの、改めてお聞かせいただけますか?
歌舞伎俳優として作品を観る、その立ち位置を超えて、やはり1つのものを極める人間としての覚悟が深く描かれている作品であると感じました。歌舞伎という題材を通して、追求する人間の心の凄さを、普遍的なものとして描き出したドラマだと思いました。
「庶民の娯楽」という歌舞伎の本質を取り戻すため、「コラボ」という武器で「生で体験してもらえる機会」を追求

――歌舞伎という舞台芸能の特徴や歴史、魅力についてお聞かせください。
伝統芸能の先輩である能楽は、室町時代にできたものです。それから時代が進み、江戸時代になって、歌舞伎は庶民の娯楽として生まれました。生い立ちは違うんですけど、のですが、歌舞伎の演目で能楽から頂戴したり、改変して作られたりしたものがあります。
そのほか、当時の瓦版に載っていた殺人事件やら心中事件やらをヒントに、作家がすぐ芝居を書きおろしたりして、そうやってどんどん作品数が増えていきました。近松門左衛門、鶴屋南北といった作家の名前はお聞きになったことがあるかもしれません。歌舞伎の演目にはいろいろなジャンルがあります。たとえば、武士を扱った「時代物」や、庶民の生活を描いた「世話物」などで、「国宝」で話題になっている舞踊作品も、歌舞伎の1つのジャンルといえます。
歌舞伎の歴史は、最初は女性から始まりました。出雲阿国という女性がリーダーを務める女性グループが、京都の鴨川の河原で踊り始めたのが歌舞伎の始まりです。江戸幕府が開かれ、戦乱の世の中が終わって庶民も生活が落ち着き、娯楽を求め始めたところに出雲阿国の一派が登場しました。
庶民たちは熱狂したそうですが江戸幕府は、歌舞伎は風紀を乱しているとして取り締まり、女性による歌舞伎が禁じられました。それならと今度は青年男性による「若衆歌舞伎」、今でいう男性アイドルグループのような歌舞伎が始まり、これも話題になったのですが、またも風紀の乱れを招くと禁じられます。こうして成人男性だけで歌舞伎をやっていくしかないとなったのですが、ゴツゴツした男だけが出てきてもあまり面白くないと。そこで、男性俳優が女性を演じる「女形」ができました。これは歌舞伎特有の、他の伝統文化にはない演出方法だと思います。こうして、時代の要請によって変化しながらも、脈々と受け継がれてきたものに加えて、現代ではアニメをはじめとする他のエンターテインメントとコラボした、新作の歌舞伎も出てきています。
――江戸時代から400年以上続いてきた歌舞伎は、令和という時代に、人々に何を伝えているのでしょうか。
もともと歌舞伎は庶民の娯楽として生まれたのですが、文化やライフスタイルが変わっていく中で、歌舞伎は庶民の娯楽というより、少し高尚なものと思われるようになっています。正直、少し手を出しにくいというイメージがあるかもしれません。
江戸時代から受け継がれてきた古典作品を大事に演じることが、歌舞伎の柱になっていることは確か。そこに、時代に合わせた変化を付け加えて、多くの方に観ていただこうとしているのが、今の歌舞伎だと思います。
歌舞伎俳優として一番大切に考えているのは、やっぱり歌舞伎は「生」で体験していただきたいということです。私たちの演技と、歌舞伎ならではの舞台装置や音楽を体験しに、足を運んでいただく。今は配信もありますが、やっぱり生で観ていただくことが一番だと思います。歌舞伎座や京都南座といった歌舞伎の劇場から、小劇場も含めいろいろなイベントや実験的な舞台をやったりもしていますので、歌舞伎ならではの美を、目の前で観ていただきたいです。たとえ言葉がわからなくても、観てかっこいい、綺麗だと思っていただける力がありますから。
――言葉がわからなくても美や魅力が伝わるという点は、インバウンドとの親和性が非常に高いと思います。外国人のお客様は多く来られているでしょうか。
インバウンド対応は力を入れていまして、外国人観光客だけが買える席や、何幕見てOKな安く座れる席などをご用意しています。歌舞伎座ではイヤホンガイドをご用意していまして、同時通訳で説明を聞きながら歌舞伎を鑑賞していただけます。
歌舞伎を広く知っていただくうえで、大事なのは「掛け合わせ」だと思っています。歌舞伎というと、難しい、わからないというイメージを持たれている方もいると思いますが、たとえばアニメであったり、ファッションであったり、アートであったり、あるいはバレエなのかオペラなのか、他ジャンルの芸能との掛け合わせ、コラボレーションをすることで、歌舞伎の敷居を下げる取り組みをしてきました。私たちはそのような舞台で、400年間培ってきた、歌舞伎をやればいい。このような表現の機会がすごく増えていますし、これからインバウンドに開いていくにも大切だと感じています。
民俗芸能としての共通性が「歌舞伎×フラメンコ」という異色のコラボレーションに結実。そして凱旋公演へ

――外国との関わりで言うと、壱太郎さんは2023年から24年にかけて、スペインとアメリカで公演されています。
2023年はスペインで、歌舞伎とフラメンコのコラボレーション興行を行いました。
以前にスペインを訪れた時に、フラメンコが生まれたと言われる、ヘレス・デ・ラ・フロンテーラという街に寄ったんです。すると、街のそこらで当たり前にフラメンコを踊っている人がいる。その様子を見て、私は歌舞伎が庶民にとって土着の娯楽だった時代を想って、こんなふうに芸能が日常に残っている国があるんだと、深く感動したんです。
歌舞伎とフラメンコには、どちらも庶民の芸能であることに加えて、もう1つ共通点があります。それは、重心が下がる舞踊であること。バレエやサンバなど、いろんな踊りと日本舞踊のコラボをやったときに、実は合わせるのが結構難しかった。というのも、西洋の踊りというのはジャンプしたり伸び上がったり、重心が上に行くものが多いんです。一方、フラメンコは地面を踏みしめるので、動きが下に向かう。これが、日本舞踊や歌舞伎の「腰を折る」とか「重心を低くする」動きと親和性があるんです。それで、すごくコラボしやすかったんですね。
こういった、土着性と舞踊としての共通性を活かして新しい表現を生み出すショーを行い、翌年のスペインはマドリードの夏のフェスティバルにもご招待いただきました。野外のフェスのような興行で踊らせていただき、すごく盛り上がりました。それで今年、日本で「イン・ヒューマン」という凱旋公演を行うことが決まっています。私をスペインへと導いてくれたアルテイソレラの皆さんと、私が脚本・振付を担当し、もちろん出演します。このように、海外で行ったこと、得たものを日本に持ち帰り、また改めて海外へ発信していくという動きを、私はとても大切にしています。
2024年は、日本舞踊家としてニューヨークに行きました。有名なバレエ曲の「ボレロ」に合わせて、歌舞伎の演目にもなっている「道成寺」を日本舞踊で表現しました。ニューヨークタイムズにも取り上げていただき、非常に意義深い公演になったと自負しています。
――そういった活動は、今後も機会があればやっていきたいと思われていますか?
はい。やはり今後の歌舞伎の可能性を拓いていくために、海外の方、そしてインバウンドのお客様に観ていただくことはとても大切だと思っています。現在、歌舞伎をご贔屓にしてくださっている方々は50代から70代の方が多いので、未来に向けた発信、種まきは常に行っていかねばなりません。種から花が咲くまでには時間がかかりますので、令和の歌舞伎俳優は、使命感を持って客層を育てることが求められていると思っています。
――舞踊の指導をされた映画「国宝」が大ヒットとなり、スペインやニューヨークでも公演を成功に導かれ、歌舞伎を背負い、広めることを壱太郎さんはずっとしてこられたことがよくわかりました。最後に、インバウンド関係者の方に向けて、歌舞伎俳優として、メッセージをいただけますでしょうか。
「歌舞伎を見るきっかけがなかなかない」というお言葉をよく耳にします。やっぱり、初めてご覧になる方々を少しでも多く引き入れることが、私たちの課題だと思っています。ですので、歌舞伎を扱ってもらうだけでありがたいと思いますし、ちょっとしたイベントでも身一つで行けるのが歌舞伎俳優ですから、何かできればと常に思っています。
歌舞伎の景色を見せるだけもできますし、踊ることも含めて、いろいろなパッケージをしつらえることができます。もちろん、大きな劇場でする歌舞伎に一番真価が表れるとは思いますが、それしかできないということではもちろんありません。場所やイベントなりのパッケージでお見せする時代だと思っていますし、海外に関しても、個人で発信できる海外公演から、もう1人増えれば男女の表現ができるとか、許される幅の中で作り上げていくことが大切だと考えています。本当にまだ見ぬ土地、行ったことのない土地で歌舞伎をすることが、自分の中での目標になっていることを、知っていただければ幸いです。
(取材・文=日野秀規/フリーライター)

・『ART 歌舞伎 2025~DEEP FOREST~』
会場 : GINZA SIX 観世能楽堂
日時 : 2025年11月8日(土)16:30~ / 19:00~
公式サイト : https://artkabuki.com
・「ART歌舞伎2025~DEEP FOREST~」
【生配信】
「ART歌舞伎2025~DEEP FOREST~」19:00公演
販売期間:2025年10月18日(土) 10:00~11月14日(金) 21:00
配信期間:2025年11月8日(土) 19:00~11月14日(金) 23:59
【アーカイブ配信】
「ART歌舞伎2025~DEEP FOREST~」16:30 / 19:00の両公演、特典映像
販売期間:2025年10月18日(土) 10:00~2026年1月15日(木) 21:00
配信期間:2025年11月15日(土)~2026年1月15日(木) 23:59
チケット情報:https://w.pia.jp/t/artkabuki/
公式サイト:https://artkabuki.com
・鍵田真由美・佐藤浩希フラメンコ舞踊団 新作公演
『イン・ヒューマン (in human)』(原作:江戸川乱歩「ひとでなしの恋」より)
日時 : 2025年11月12日(水)19:00 / 11月13日(木)14:00
会場 : せたがやイーグレットホール 世田谷区民会館
料金 : SS席12,000円 / S席10,000円
http://arte-y-solera.com/new/11398/
・「當る午歳 吉例顔見世興行」
会場 : 南座
2025年12月1日(月)初日 ~ 25日(木)千秋楽
ご観劇料 : 一等席26,000円
https://www.kabuki-bito.jp/theaters/kyoto/play/895
・「壽 初春歌舞伎特別公演」
会場 : 松竹座
2026年1月7日(水)初日~25日(日)千秋楽
ご観劇料 : 一等席16,000円
https://www.kabuki-bito.jp/theaters/other/play/959
・「あらしのよるに」
会場 : 博多座
2026年2月7日(土)初日~20日(金)千秋楽
ご観劇料 : A席15,500円、平日夜A席14,000円
https://www.kabuki-bito.jp/theaters/other/play/945
・「花形歌舞伎 特別公演」
会場 : 南座
日程等他詳細未定
https://www.kabuki-bito.jp/theaters/kyoto/play/952