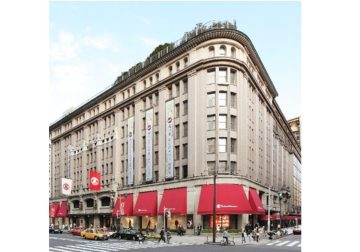●この記事のポイント
・インバウンド観光客の間で地方の小さな町を散策する体験型ツアーが増加傾向にある
・リピーター客が多く、地元の職人や住民との交流を重視する少人数制ツアーが人気を集めている
・観光地分散化により、オーバーツーリズム解消と地方活性化の両立が期待されている
今年1~6月の訪日外国人数(推計値)が2151万8100人(日本政府観光局発表)となり、過去最も速いペースで年間2000万人を超え、7月も前年同月比4.4%増の343万7000人と同月として過去最多となるなど、引き続きインバウンドの増加傾向が続いている。訪日外国人の観光の傾向としては、1回目の訪問時は、いわゆるゴールデンルートと呼ばれる東京・大阪・京都を回るかたちが一般的だが、来日2回目以上のリピーターともなると、寿司店で寿司づくりをしたり、日本の伝統芸能に一日入門したり、雪かきをしたりといった、さまざまな体験系ツアーを楽しむ人も増えている。また、観光地ではない地方の小さな街で、数時間から丸一日、地元の人々が親しむ場所や店舗をめぐる参加者1名~数名程度のツアーも、じわり人気が出てきているという。利用者はSNSなどで見つけて申し込みをするケースが多いようだが、どのようなツアーなのか。また、その魅力は何なのかを追ってみたい。
●目次
- 一般的なゴールデンルートにはあまり興味がない
- 地元の職人さんがオーガニックに育てた植物で藍染め体験
- 1人ひとりのお客様にもカスタムメイドのツアーを作って提供
- 1回来ると本当にファンになってくださる方が多い
一般的なゴールデンルートにはあまり興味がない
インバウンドの間で地方の小さな町を散策する旅行ツアーの利用が増加している背景は何か。旅行業務取扱管理者および通訳ガイドとして佐野市観光協会とも連携しながら栃木県でインバウンド観光事業を展開しているローカルリビングツアー代表の竹田祐子氏は次のように説明する。
「絶対数としてはまだまだ少ないですが、徐々に興味がある方が増えています。一般的なゴールデンルートにはあまり興味がない方や、もう一度見ているから2回目の日本旅行で違う場所に行きたいとおっしゃる方、日本の文化に深い興味がある方が、地方の都市に来ていただく傾向にあります」
こうした需要を受けて、地方自治体やツアーガイド会社も新たな取り組みを始めている。
「地方の自治体やツアーガイド会社が、地方の特色を活かしたツアーを提供し始めています。観光地ではない場所で体験をしていただく、地元の方と交流をしていただく体験を売りにしたツアーのプロモーションをかけている状況です」
地元の職人さんがオーガニックに育てた植物で藍染め体験
具体的にどのようなツアーが人気を集めているのだろうか。
「非常に人気があるツアーは、ローカルな街での藍染め体験です。藍染めの蓼藍という植物を、現地で職人さんがオーガニックに育てていらっしゃって、そこですくもを作り、それで染めて、そのすすぎの過程を川で行うのです。夏などは、お客様に川に裸足で入っていただき、ご自分が染めたものをすすいでいただくいう体験が非常に好評です。たまに川遊びしている地元のお子さんもいて、やはり日本の自然の中で蛙を捕まえたり、小さい魚を見つけたりして、そういう光景も喜んでいただけます。お自分が着るTシャツやスカーフなどをデザインして染め、当日お持ち帰りになれます」
1人ひとりのお客様にカスタムメイドのツアーを作って提供
これらのツアーは通常、丸一日かけて実施される。参加者の要望に応じて柔軟にプログラムを組んでいるという。
「少なくとも日帰りで、東京からのお客様にはなるべく地元に貢献したいので宿泊していただけるようにしていますが、例えば東京で1週間宿泊を取っている方などは、1日でも満足して貰える体験プログラムを用意しています。栃木県内までは大体1時間半、2時間で来れるので、朝10時ぐらいに駅でピックアップして、夕方6時ぐらいに駅にお送できます。
食事についても地元の特色を活かした配慮をさせていただいております。なるべく旬の野菜などを使った地元のお店、地元のものが食べられる野菜中心のレストランなどで食事をとっていただいております。お客様の要望を聞いた上で、例えばお肉を食べないお客様や、グルテンがダメなお客様などのご要望に応じて、レストランを選定しています。そういうレストランに行ったら、ただ食べるだけではなくて、作っている方ともお話を少ししていただいて、『これはどういうものですよ』といったご説明や、『これはどこで採れたものです』ということをお伝えしています。お客様が『私これすごい好きだから、ぜひレシピを教えてください』といった感じで、色々と会話が生まれることもあります」
参加者数は少人数制を基本としている。
「本当に少ないんです。以前は2名以上での受付でしたが、1名の方もたくさんいらっしゃって、1人で栃木に来たいという方をお断りするのは申し訳ないので、1人の方も受け入れています。平均2名で、多くて4名程度のご家族です。お友達やカップルの2名が1番多いですね。それぞれのお客様にカスタムメイドのツアーを作って提供しております」
参加者の国籍は非常に多様だという。
「本当にいろんな国の方がいらっしゃいます。私はバックグラウンドがアメリカなので、アメリカのお客様が来てくださるかなと思っていましたが、初めの頃はヨーロッパやアジア圏の方ばかりでした。南米、アフリカの方もいらっしゃいますし、ブラジル、オーストラリアからも多くの方が参加されています。今、日本が注目されている観光地として、ネット上には多くの日本に関する情報が出ていて、すごく評判が良いので、それで行ってみたいという気持ちを持つ人が多いのだと思います」
1回来ると本当にファンになってくださる方が多い
特筆すべきは、リピーター率の高さである。
「1回来ると本当にファンになってくださる方が多くて、リピーターの方もいらっしゃいます。シンガポールの方などはすぐ来れるので、アジア圏の方は割と来てくださるのですが、遠い方ですとドイツの方も1年の間に2回も来てくださって、『すごく気に入った』と言ってくれています。そういう方は、人に会いに来るんですね。『今度はボーイフレンドと一緒に行くから、紹介したい』といった感じで来てくださったりします。栃木のこの雰囲気、日本の何気ない日常がすごく楽しいということで、目的地に行く前にちょっと寄ってみる、予定表に入っていないところに寄って河川敷でピクニックしたりとか、そういうちょっとしたことがすごく思い出に残るようです」
集客方法については、SNSとウェブサイトが中心となっている。
「インスタグラムと私のウェブサイトのお問い合わせにメールをくださったりしています。私の場合は栃木県佐野市の観光協会、観光推進課と一緒に活動している部分もありますので、そちらの案件をお手伝いさせていただくケースもあります。弊社のサイトは、地元の職人さんやアーティスト、自然、伝統文化などを交えて栃木県を紹介しているので、そういうものに共感してくださる方が問い合わせしてくださいますね」
今後の展開について、竹田氏は地域間連携の可能性に言及する。
「私がご案内できる地域は限られているので、地方で同じようなことをしている、例えば近隣の群馬や福島、宮城といった、あまり観光客が来なくてこれから盛り上げていきたいような場所と連携して、ルートを広げたいと考えています。『これから2週間いるんだけど、他の場所にも連れて行って』といったお話もたまにありますので、東だけでなく西に行くとか南に行くとかでも、そういう方と繋がっていければと思います」
最後に、今後の日本のインバウンド対応について竹田氏は次のように提言する。
「今は本当にオーバーツーリズムが問題になっているので、それを打開しないと互いに詰まってしまうと思います。例えば初めて日本に来られる方のなかには『絶対に京都へ行かなければならない』と思っている方もおられますが、混んでいる時に行ったら、もう2度と行きたくないと感じてしまいますよね。一方で、京都に住んでいる方も普通の生活が回らないような状態になっているので、それを打開する必要もあります。地方にはたくさん良いところがあるので協力して、インバウンドの受け入れ先を分散していかないと本当の日本の良さというのは分かってもらえないでしょう。日本が観光大国を目指すなら、これまで注目されなかった地域を紹介し、新しいユニークな旅の形を提案していくことが大切だと思います。
地方には外国人の方が満足できるような宿泊施設が少ないという課題があります。私もいろいろと視察に伺うのですが、『必ず来てもらえるなら、改修するけれども』『対応できるスタッフがいない』といったお声をよくいただきます。 ただ、実際に改修したとしても外国人のお客様が必ず増えるとは限らず、その判断は非常に難しいのが現状です。 だからこそ、最終的には“人の力”で補っていくしかないと考えています。地元の250年続いている老舗の10代目の女将さんと親しくさせていただいているのですが、彼女の旅館は小さくてゴージャスな感じはないのですが、とにかく女将さんが明るくて、言葉が通じる・通じないの問題ではなく、すぐお友達になってしまうんです。建物や立地の条件以上に、その土地ならではの文化や、地元の人々の温かさといった魅力でカバーできる部分も、かなりあるのではないでしょうか」
(文=BUSINESS JOURNAL編集部)